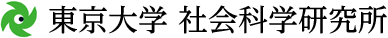研究
社研セミナー
危機言説の政治学 ―北朝鮮問題と日本安全保障政策の変遷の再検討―
セバスティアン・マスロー(東京大学社会科学研究所)
日時:2025年4月8日(火) 15時~16時40分
場所:
ハイブリッド開催
(センター会議室(赤門総合研究棟 5F・詳細地図 )/オンライン(Zoom))
使用言語:日本語
報告要旨
本報告では、近年の日本安全保障政策変化の過程における北朝鮮問題の影響について分析する。2017年、第二次安倍政権は朝鮮半島情勢が緊迫していた最中に「国難」を掲げながら、危機対応のための安全保障政策をさらに改革することを確約し、衆議院を解散し、総選挙の圧勝により再選を果たした。「国難」言説の核心であった北朝鮮問題は、拉致問題の発覚を契機として、安倍晋三をはじめとする保守勢力が国家の機能不全を指摘しながら「戦後レジームから脱却」を掲げたことにより、その拡大と定着を導いた。そして、2012年以降、安倍らは安全保障政策の大幅な変更に成功したのである。
したがって本報告は、冷戦後、北朝鮮問題とりわけ拉致問題が国内政治に与えた影響を再検討し、日本の安全保障政策の変容を導いた政治的変化を追跡する。そのため、本報告は、コリン・ヘイ(Colin Hay)による「危機」の言説形成の政治過程と国家制度の再編を分析枠組みとして応用しながら、1990年代以降とりわけ第1次および第2次安倍政権下の政策を変化させた言説形成の政治過程を分析する。ヘイはこの枠組みを用いて、1970年代後半のイギリスの社会的・経済的危機とサッチャー政権という保守政権の長期化に伴う新自由主義的国家再編の関係を分析した。このような冷戦後の国内政治におけるイデオロギー対立やエリート間の権力関係を再編させる枠組みを現代日本の政治に応用することにより、第二次安倍政権の長期化と政治制度の変化の要因およびメカニズムをより正確に把握することができる。
このように、日本の政治に焦点を当てながら日朝関係を分析し、「危機言説の政治学」という観点から北朝鮮問題と日本の政治的変化の相関関係の再考を試みる。そのため本報告は、「戦後レジーム」論の起源とその展開に着目しながら、日朝関係を軸として、冷戦後日本の安全保障政策変化、とりわけ集団的安全保障論、敵基地攻撃能力の保有との関係を言説形成と政策変化の具体例として分析する。