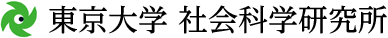研究
社研セミナー
労働におけるハラスメントの法的定義及び法的規律――日仏カナダの比較法研究
日原雪恵(東京大学社会科学研究所)
日時:2025年6月10日(火) 15時~16時40分
場所:
ハイブリッド開催
(センター会議室(赤門総合研究棟 5F・詳細地図 )/オンライン(Zoom))
※所内限定の開催となります。
使用言語:日本語
報告要旨
本報告は、報告者が現在進めている労働におけるハラスメントの法的定義及び法的規律に関する比較法研究の成果の一部を紹介することを目的とする。報告者の助教論文「労働におけるハラスメントの法的規律――セクシュアル・ハラスメント、差別的ハラスメント及び『パワー・ハラスメント』に関する日仏カナダ比較法研究」法学協会雑誌140巻1号1頁・同3号347頁・同5号547頁・同7号829頁・同9号1193頁・同11号1463頁、同141巻1・2号1頁(2023年~2024年)を基にしつつ、その後の動向や明らかになった新たな研究課題を含めて検討を行う。
日本では、セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント等が社会的に問題となり、不法行為等の訴訟で言及されるようになった後、均等法や労働施策総合推進法等にパッチワーク的に措置義務が立法されるという展開を辿ってきた。比較法研究でも、セクシュアル・ハラスメント と「パワー・ハラスメント」(諸外国では「いじめ(bullying、 mobbing)」、「心理的ハラスメント(harcèlement psychologique)」等と呼ばれる) が別々に研究されており、横断的に検討したものは少ない。労働におけるハラスメント全体をどのような規律根拠(保護法益)に基づき、どのような規律手法で規律すべきかに関する基礎的な検討はあまり行われておらず、様々なハラスメントの共通点と相違点を踏まえた議論の(再)整理が必要である。
以上のような問題意識の下、本報告では、議論の蓄積のあるフランスとカナダ(ケベック州・オンタリオ州)を対象とする比較法研究の成果を報告する。労働におけるハラスメントの法的定義の構成要素と規律根拠(保護法益)および予防・禁止・救済に関わる規律手法(立法形式、名宛人等)を整理し、検討対象国で法がどのようにこの問題に対処しているかを明らかにする。そのうえで、日本法への示唆を示す。