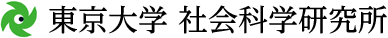研究
社研セミナー
祭りにおける身体と「美しさ」―「佐原の大祭」とヴァナキュラー美学の民俗学—
塚原 伸治(東京大学大学院総合文化研究科)
日時:2025年12月9日(火) 15時~16時40分
場所:
ハイブリッド開催
(センター会議室(赤門総合研究棟 5F・詳細地図 )/オンライン(Zoom))
使用言語:日本語
報告要旨
本報告は、千葉県香取市「佐原の大祭」における山車の曳きまわしを対象に、担い手たちの身体技法と審美的感覚に注目し、ヴァナキュラーな美学のありかたを描き出す試みである。山車を「ゆっくり」「止めず」「軸をぶらさない」ように曳くという微細な動作の連続には、外部からは見えにくいが、共同の身体が生み出す緊張と快楽が潜んでいる。そこでは、反復のなかに差異を見いだす感覚や、「よさ」をめぐる相互承認の基準が、美的実践として共有されている。
そこで本報告では、近年報告者が手がけてきたいくつかの論考を参照しつつ、このような審美的な身体行為の分析を通して、従来の枠組みを相対化することを目指す。民俗学の古典的議論――たとえば柳田國男が示した観客のまなざしに関する洞察や、折口信夫による芸能の生成論――は、祭礼と芸能が「儀礼」と「それを審美的に眺めるまなざし」との関係によって成り立つことを示唆していた。他方で、戦後の関心は、起源論的な民間信仰の研究や制度・組織の歴史分析へと傾き、身体や情動、美学といった感覚的次元は相対的に扱われにくくなっていった。
本報告の目論見は、こうした古典の審美的視座を担い手の実践へと引き寄せながら再考することである。その際には、アメリカ民俗学における「パフォーマンス論的転回」と呼ばれる動向を踏まえつつ、その後の世代による民俗文化と美学の再検討にも目を向ける。これらの議論を参照しながら、祭礼を社会構造や制度の単なる反映ではなく、人々の身体と相互行為のなかで生成する美的コミュニケーションとして捉える視点を提示する。この視点を通して、民俗学における身体・美学・情動への関心をあらためて考え、佐原の事例を手がかりに、祭りを実践的な美的表現として、あるいは美的コミュニケーションとして再定位することを試みる。