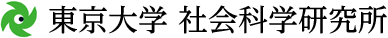案内
- トップ
- 社研卒業生の現在
社研インタビュー
社研卒業生の現在(いま)
このページでは、社研卒業生の現在と題しまして、今まで社研にある時期在籍されて、今は多方面で活躍されている皆様をご紹介しています(プロフィールにあるご所属・ご職位はインタビュー当時のものです)。
最新の記事

石田 雄さん
「社会科学研究所を定年(当時60才)で退職してから35年になるので思い出すことも多いが、生きている限りは果たさなければならないと考えている戦中派としての戦後責任についてだけ述べる。」
(2019年5月30日掲載)
これまでの記事

原口佳誠さん
「法に対する社会科学的な研究関心の芽生えは、社研の自由闊達な学際的気風がきっかけであったように感じています。」
(2019年4月18日掲載)

関沢洋一さん
「わずか2年間の社研の在籍でしたが、とても有意義だったと思います。もしかしたらこの2年間が私の人生を変えてしまったのではないかと思うことさえあります。」
(2018年12月10日掲載)

張馨元さん
「While more and more works on economics are done utilizing secondary data, I continue conducting fieldwork following the research style which Prof. Suehiro described as “research should be done on foot (研究は足でやる)”」
(2018年10月2日掲載)

中村民雄さん
「私の社研エンジョイ法は、ジャズ・カルテットのセッションよろしく、法学、政治学、経済学それぞれの美学と技を活かして一つの共通のテーマ(音楽)を研究(演奏)しようと相手を誘い出すものになった。」
(2018年7月13日掲載)

相澤 真一さん
「語学力が当初足りなくても、丁寧に仕事をすることで道を切り拓くことを社研で覚えたことは、多くのことにつながりました。2011年に研究者派遣の第一号として私がオックスフォードに研究滞在したこと、今年度にはHigh School for All in East AsiaとしてRoutledge社から英語書籍を出版できたこと、中京大学で頂いた在外研究の機会では、社研とも学術交流のあるベルリン自由大学日本研究所にて研究滞在したこと、このすべての国際的な活動の萌芽がこの仕事のなかにありました。」
(2018年6月13日掲載)

松村智雄さん
「講義をする中で、主な研究分野を基盤にして、それをいかにより広い研究分野の中に位置付けられるかということを絶えず考えるようになった。それが自身の研究分野の存在意義となるからだ。華人について研究することは、諸民族の持続的な共生のモデルについて考えることではないか。またそれは、国民国家中心ではない「地域の歴史」を研究することにつながる。」
(2017年12月19日掲載)

高橋五月さん
「私は赤門棟5階がとにかく好きでした。各部屋、各自でやっていることは色々でしたが、「赤門棟5階」は長屋的(?)コミュニティーを形成していたような気がします。赤門棟ランチ会なるものも不定期に開催され、いつも涙を流しながら笑っていたことを記憶しています。」
(2017年9月27日掲載)

大島潤二さん
「社研は、理工系の大規模部局と違い教職員数が少なく、先生と事務との距離も近いため、アットホームな雰囲気で連帯感があるところだと思います。」
(2017年9月27日掲載)

清弘ひかりさん
「社研の図書室では図書がとても大切にされており、図書の保存や補修についての研修や講習会、講演会等に数多く参加させていただきました。異動の直前には資料雑誌業務も担当させていただき、業務の幅を広げることができました。社研で学ばせていただいた知識や経験は、図書館職員としての私の大切な基盤となっています。」
(2017年3月27日掲載)

Thomas Blackwoodさん
「Probably the strongest impression I have from my time at Shaken is the degree to which Shaken is a truly egalitarian (フラット) institution, where all members—faculty or staff, full professor or research assistant—treat each other with respect. I have never been in an institution before or after, in Japan or America, where one’s status was as seemingly immaterial as at Shaken. 」
(2017年3月27日掲載)

荒見玲子さん
「改めて振り返ると、社研はとてもフラットな職場であると同時に、若手の育成システムがとても整っているところでした。セミナーや研究活動の過程で助教でもきちんと意見を求められ、学際的に活発な意見が飛び交う中で、むしろ自分のディシプリンの守備範囲がどこで、何が強みで何が弱みなのかを強く意識するようになったことは、私のキャリア上の得難い経験だったように思います。」
(2016年12月22日掲載)

小森田秋夫さん
「昨今、学長のリーダーシップが強調されています。学長と所長とでは同じではありませんが、社研というところは、伝統となった独自の気風があり、所員がそれぞれの場所で自律的かつ積極的に活動し、それを信頼することのできる職場でした。」
(2016年12月22日掲載)

菅万理さん
「着任当時の社研では、2005年から 「希望学」プロジェクト、2006年から「働き方とライフスタイルの変化に関する全国調査」と、社研を特徴づけるような大プロジェクトが躍動していました。私にとって社研とは、緻密に掘り下げていく研究と、分野を超えて広く社会に発信する研究のクロスロードのような場所でした。」
(2016年9月20日掲載)

上村泰裕さん
「社研の助手として過ごした2001年からの3年間は、現在に至る私の仕事の土台になっていると感じます。研究テーマについても、研究者のネットワークの点でも、社研時代に得たきっかけがその後の展開につながりました。」
(2016年9月20日掲載)

佐藤慶一さん
「「震災の記憶」オーラルヒストリー調査では、消防関係の方などにお話をうかがい『〈持ち場〉の希望学 釜石と震災、もう一つの記憶』東大社研、中村尚史、玄田有史 編(東京大学出版会 2014年)の第4章にしていただきました。直接当事者から震災時の悲しみなど胸に迫るお話をうかがったことは、自身の研究スタイルのみならず、ものの見方や考え方にも影響があったものと思い返されます。」
(2016年6月29日掲載)

佐藤由紀さん
「社研は、研究者としてしなやかに強く生きていきたい、という想いを育んでくれた場所です。その想いを胸に、研究者としての自分と、教員としての自分の接点を上手につなげていくことが、今の私の課題です。」
(2016年6月29日掲載)

和田春樹さん
「最後に私の仕事は、「東北アジア共同の家」の建設を提案するところにまで進みました。社研を退職するときの最終研究会報告で私はこの構想について話しました。だから、近年社研が「東アジア共同体」の共同研究をされているのを知って、とてもうれしかったのです。 」
(2016年3月30日掲載)

石黒久仁子さん
「社研での業務、研究活動、そして先生方、職員の皆さん、同僚の研究者の皆さんとそれら業務・研究活動を通じてご一緒することができたのは、現在の私の活動とキャリアを支えている、一番の土台であり財産であると思います。」
(2016年3月30日掲載)

相澤美智子さん
「私が社研に職を得たキッカケは、2000年10月のある日に、高校の同級生からもらった1通のメールでした。 」
(2015年12月25日掲載)

郭舜さん
「広い個室を割り当てられたものの、書架にほとんど本もなく、がらんとした空間をもてあましているようなかたちでしたが、そうした感覚も徐々に薄れ、生活に慣れてきました。一員となってみると、社研は事務室や図書室の方々も含めて、一体となって動いている組織であるということを実感しました。」
(2015年12月25日掲載)

金成垣さん
「大学院修了後、社研での助教の3年間は、それまでの自分がやってきた比較福祉国家研究をさらに広くかつ深く展開していくうえで非常に貴重な時間となりました。」
(2015年9月4日掲載)

板倉奈緒美さん
「男女共同参画の流れの中で、あの悩んでいた日々は何だったのだろうという位、最後はあっという間でした。後に続く女性に、「板倉さんが頑張っているから自分も頑張れるかもしれない。」と思ってもらえるよう、これからも精進していきたいと思っています。」
(2015年9月4日掲載)

中澤 渉さん
「日本の社会科学の将来は、SSJDAのあり方如何にかかわると言っても過言ではないと思います。現在の担当者の方にもその思いを引き継いでもらいたいと思うと同時に、社研の今後の発展を願ってやみません。」
(2015年7月6日掲載)

横山由香里さん
「前々から、社研でお仕事をされていた先輩が「社研は学際的な機関で面白い!」と仰っていたので、データアーカイブでの学術支援専門職員のお話を頂戴した時は、とてもうれしかったです。」
(2015年7月6日掲載)

広渡 清吾さん
「社研で最後のプロジェクト研究は、「希望学」への参加でした。専門家が誰もいない、アイディアをだしあう研究がとても魅力的で、責任者のリーダーシップが抜群でした。」
(2015年3月31日掲載)

三浦 まりさん
「私が社研を去るのと入れ違いで、バークレー時代にお世話になったGregory Noble先生が着任され、社研は英語圏での日本政治研究の研究拠点として益々重要な役割を果たしているように思います。」
(2015年3月31日掲載)

大井 方子さん
「社研では労働関係の先生方も多く、社研の外で開かれている労働関係の研究会にも呼んで頂くようになったことから、労働関係の研究をもっとやっていこうと思うようになりました。」
(2015年1月8日掲載)

門馬 清仁さん
「所長はじめ諸先生方には、社研独自の様々な自己啓発支援制度をつくってくださったことに大変感謝しております。私は、在職中、継続して韓国語を学ばせていただきました。」
(2015年1月8日掲載)

藤森 宏明さん
「着任当初は業務の内容自体を把握するのにとても苦労し、自他ともにハラハラしながらも多方面の方々からの叱咤激励の中、何とか働いていたように思います。」
(2014年10月3日掲載)

山崎 由希子 さん
「編集の仕事については社研で得た研究者情報や原稿依頼のマナー知識がとても役に立っていますし、またこちらでの仕事で知り合った研究者の方が社研をご存じであったり、社研の持つネットワークの広がりを感じます。」
(2014年10月3日掲載)

石倉義博 さん
「社研着任時には、2000年問題が話題となっていた時期でもあり、古い教員用端末やサーバシステムの更新を大慌てで行なったのも懐かしい思い出です。」
(2014年7月17日掲載)

永井暁子 さん
「社研勤務時代の知り合いは現在でも重要な研究仲間です。私の研究生活にとって貴重な機会を与えてくれたことをとても感謝しています。」
(2014年7月17日掲載)

橘川武郎 さん
「3.11後、原発問題や震災復興をめぐって社会的に発言する機会が増えましたが、その際、「希望学」プロジェクトを通じて福井・嶺南や釜石の方々と直接お話させていただいた経験が、自分の視座を作り上げる基盤となりました。」
(2014年3月17日掲載)

保坂美和子 さん
「図書委員会は教官と図書職員によって構成されていましたが、会議ではいつも、立場の違いを超えて率直に意見を述べられる雰囲気がありました。」
(2014年3月17日掲載)

菊池哲彦 さん
「今回、自分の話が社研ウェブ・サイトの「コンテンツになる」というのは、なんとなく気恥ずかしい気がしています。「コンテンツにする」のが仕事でしたので… 。」
(2013年12月12日掲載)

高松香奈 さん
「社会科学研究所は私の人生に強い影響を与えた機関であり、貴重な「出会い」を下さった「場」です。」
(2013年12月12日掲載)

松本秀幸 さん
「今の仕事に従事できるのも、国際交流の職務の機会を与えて頂いた社研のおかげだと思っています。」
(2013年 9月13日掲載)

黒田祥子 さん
「教育と研究という両輪を回す現在のスタイルを楽しむことができているのも、社研での研究に没頭した2年間があったからだと思います。」
(2013年 9月13日掲載)

土屋ともよ さん
「定年退職前の3年間弱でしたが、研究分野を複数の視点から考察なさる先生方が職員にも気軽に話し掛けて下さるすばらしい環境で過ごせました。」
(2013年 6月20日掲載)

岡部恭宜 さん
「社研は、私が半人前ながらも研究者として勤務した最初の組織であり、博士論文を完成させ、それを本として出版した場所でもありました。」
(2013年 6月20日掲載)

山崎広明 さん
「今思えば、1990年4月1日は、社会科学研究所が新たなスタートを切る画期となる日だったのではなかろうか。」
(2013年3月14日掲載)

金井郁 さん
「4年間の社研在籍は、研究者として非常に恵まれたスタート地点にいたのだ、と改めて感じています。」
(2013年3月14日掲載)

福田祐子 さん
「社研を卒業する時は悲しかったのですが、卒業生にもOpen な社研ですから、それに甘えて、現在でも社研に出入させていただいています。」
(2012年12月21日掲載)

上神貴佳 さん
「社会科学のさまざまな分野の研究者が一つのフィールドを共有し、ともに研究を進めるというのも、社研の真骨頂なのではないかと思います。」
(2012年12月21日掲載)

古谷眞介 さん
「彼らと苦楽をともにできたことが、私の財産になっています。社研での経験が大学で働くうえでの参照基準となっています。」
(2012年10月 1日掲載)

村上あかね さん
「格差や雇用の問題を地域の特性、ジェンダー、歴史など、多面的かつ総合的に捉える視座を得たことは、私の現在のキャリアにとって重要な転機だったといえます。」
(2012年10月 1日掲載)

武部三枝子 さん
「在職中に一番印象に残った仕事は、何と言っても耐震補強工事です。図書室のスタッフはもとより、事務室の方々、教員の方々の支援に助けられながら、無事引越しを終えることができました。」
(2012年 6月25日掲載)

佐藤朋彦 さん
「統計を担当する国の行政機関は、日々多くの統計調査を実施していますが、当時はまだデータアーカイブに相当する機関はなく、職員の知識も充分ではありませんでした。」
(2012年 6月25日掲載)

柴垣和夫 さん
「30余年の社研生活で一番充実していたように思えるのが助手時代です。」
(2012年 3月13日掲載)

二階堂有子 さん
「社研からはチャンスを頂いてばかりでしたが、それらの経験がその後の論文や現在大学で担当している講義に活かされていることは言うまでもありません。」
(2012年 3月13日掲載)

大森佐和 さん
「社研という研究が中心の、いつも研究上での刺激を得られる環境に身を置き続けることができたために、博士論文を仕上げる事が出来たのだと思います。」
(2011年12月27日掲載)

石川耕三 さん
「社研での5年間は、将来および経済的な不安を抱えつつも、他方で責任は限定されているという「モラトリアム」期間であったと言えると思います。」
(2011年12月27日掲載)

三輪哲 さん
「在職した4年間について非常に充実した日々だった、と振り返るのはあながち嘘ではありません。たとえそれが、常に駆け足で走ることを余儀なくさせるものだったとしても。」
(2011年9月27日掲載)

松浦民恵 さん
「社研での1年10ヶ月は、研究者としてのキャリアのなかで、研究に向き合い、生みの苦しみを味わうことができた特別な期間でした。」
(2011年9月27日掲載)