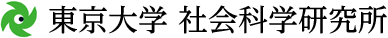スタッフ
スタッフ
飯田 高 (IIDA Takashi)

| 所属部門 | 比較現代法部門 教授 |
|---|---|
| 専門分野 | 法社会学、法と経済学 |
| iida-t[at]iss.u-tokyo.ac.jp
[at]を@に置き換えてください。 |
経歴
| 2019年4月 - | 東京大学社会科学研究所教授 |
| 2015年4月 -
2019年3月 |
東京大学社会科学研究所准教授 |
研究テーマ
- 1法の効果についての実証的・方法論的研究
Empirical and methodological study on the effect of law in society - 2社会規範の発生と変容、および法と社会規範の相互関係に関する理論的・実証的分析
Theoretical and empirical study on the emergence/transformation of social norms and the interrelationship of law and social norms - 3法や法現象のネットワーク分析
Network analysis of law and legal phenomena - 4法過程における社会科学の利用(Study on the use of social science research and data in legal process and its consequences)
Study on the use of social science research and data in legal process and its consequences - 5法律専門家の役割についての調査研究
Research on the role of legal professionals
主要業績
- 「所有権法の動態を可視化する」『法社会学』91号,2025年3月,59–72頁.
- 「ロジックモデルに関する雑感」『地方自治』928号,2025年3月,2–16頁.
- 「司法書士に対する期待と満足度:ある社会調査のデータから」『市民と法』151号,2025年1月,95–100頁.
- 「弁護士依頼者関係と弁護士倫理:心理と環境」髙中正彦=石田京子編『論究 新時代の弁護士』,弘文堂,2024年10月,381-398頁.
- 「抽象化と数量化:法現象をどう測定するか」『法社会学』90号,2024年3月,36–53頁.
- 「司法はどのように人を救えるのか」『法学教室』522号,2024年3月,6–11頁.
- (齋藤哲志・瀧川裕英・松原健太郎と共編)『リーガル・ラディカリズム:法の限界を根源から問う』有斐閣,2023年8月.
- (近藤絢子・砂原庸介・丸山里美と共編)『世の中を知る、考える、変えていく:高校生からの社会科学講義』有斐閣,2023年7月.
- 「法によるインセンティブとクラウディング・アウト」『法の支配』209号,2023年5月,87–104頁.
- 「法の構造の定量的分析:民事法を素材として」日本法社会学会編『法社会学の最前線』有斐閣,2023年5月,3–25頁.
- (J. Babbと共編)Dealing with Crisis: The Japanese Experience and Beyond, Edward Elgar, May 2023.
- 「高齢者にとっての民事裁判」佐藤岩夫=阿部昌樹=太田勝造編『現代日本の紛争過程と司法政策:民事紛争全国調査2016-2020』東京大学出版会,2023年3月,515–533頁
- 「本書の目的と方法:『民事紛争全国調査2016-2020』プロジェクトの概要」佐藤岩夫=阿部昌樹=太田勝造編『現代日本の紛争過程と司法政策:民事紛争全国調査2016-2020』東京大学出版会,2023年3月,1–21頁(共著者:佐藤岩夫,高橋裕)
- "The Citizen Preferences-Positive Externality Trade-off: Survey Study of COVID-19 Vaccine Deployment in Japan," SSM - Population Health 19: 101191 (Co-authored with Keisuke Kawata and Masaki Nakabayashi), doi.org/10.1016/j.ssmph.2022.101191, September 2022.
- "Mobile Health Technology as a Solution to Self-Control Problems: The Behavioral Impact of COVID-19 Contact Tracing Apps in Japan," Social Science & Medicine 306:115142 (Co-authored with Masahiro Shoji, Susumu Cato, Asei Ito, Kenji Ishida, Hiroto Katsumata, and Kenneth Mori McElwain), doi.org/10.1016/j.socscimed.2022.115142, August 2022.
- 「くじによる財の配分:リスクの観点から」瀧川裕英編著『くじ引きしませんか? デモクラシーからサバイバルまで』信山社,2022年5月,185–232頁
- 「『社会のルール』と『法』」法学セミナー807号,2022年4月,8–13頁
- 「市場・企業」佐藤岩夫=阿部昌樹編『スタンダード法社会学』北大路書房,2022年3月,232–241頁.
- 「新型コロナウイルス感染症に関する壮年パネル調査:概要と記述統計分析」(共著者:石田賢示,伊藤亜聖,勝又裕斗,加藤晋,庄司匡宏,ケネス・盛・マッケルウェイン),社会科学研究73巻2号,2022年3月,95–125頁.
- 「EBPMとDXは計画行政をどう変えるか」計画行政45巻1号,2022年2月,27–32頁.
- 「ソフトローとは何か」法学教室497号,2022年2月,10–14頁.
- “Vaccination and Altruism under the COVID-19 Pandemic,” Public Health in Practice 3(12):100225 (Co-authored with Susumu Cato, Kenji Ishida, Asei Ito, Hiroto Katsumata, Kenneth Mori McElwain, and Masahiro Shoji) , doi./org/10.1016/j.puhip.2022.100225, January 2022.
- “Social Media Infodemics and Social Distancing under the COVID-19 Pandemic: Public Good Provisions under Uncertainty,” Global Health Action 14(1) (Co-authored with Susumu Cato, Kenji Ishida, Asei Ito, Hiroto Katsumata, Kenneth Mori McElwain, and Masahiro Shoji), doi.org/10.1080/16549716.2021.1995958, November 2021.
- “Variations in Early-Stage Responses to Pandemics: Survey Evidence from the COVID-19 Pandemic in Japan,” Economics of Disasters and Climate Change, (Co-authored with Masahiro Shoji, Susumu Cato, Kenji Ishida, Asei Ito, and Kenneth Mori McElwain), doi.org/ 10.1007/s41885-021-00103-5, November 2021.
- 『デジタル化時代の「人間の条件」:ディストピアをいかに回避するか?』(共著者:加藤晋・伊藤亜聖・石田賢示)筑摩選書,2021年11月,256頁.
- 「訴訟当事者の声を拾うには:民事訴訟調査のサンプリングと回答率について」法と社会研究6号,2021年9月,103–128頁.
- “Prosociality and the Uptake of COVID-19 Contact Tracing Apps: Survey Analysis of Intergenerational Differences in Japan,” JMIR Mhealth Uhealth 9(8):e29923, (Co-authored with Masahiro Shoji, Asei Ito, Susumu Cato, Kenji Ishida, Hiroto Katsumata, and Kenneth Mori McElwain), doi.org/10.2196/29923, August 2021.
- 「市場におけるルールと私的組織:市場ガバナンスに関する試論」金融研究40巻3号,2021年7月,1–44頁.
- 「自助・共助・公助の境界と市場」経済分析203号,2021年7月,285–307頁.
- 「くじとリスク:ミクロレベルの一考察」法と哲学7号,2021年6月,119–144頁.
- 『現場からみる障害者の雇用と就労:法と実務をつなぐ』(共著者:長谷川珠子・石﨑由希子・永野仁美)弘文堂,2021年4月,375頁.
- 「法の構造と計量分析」社会科学研究72巻2号,2021年3月,3-25頁
- 「法過程における社会科学」司法研修所論集130号,2021年3月,184–225頁
- “The Bright and Dark Sides of Social Media Usage During the COVID-19 Pandemic: Survey Evidence from Japan,” International Journal of Disaster Risk Reduction 54 (Co-authored with Susumu Cato, Kenji Ishida, Asei Ito, Hiroto Katsumata, Kenneth Mori McElwain, Masahiro Shoji) , doi.org/10.1016/j.ijdrr.2020.102034 , January 2021.
- 「弁護士の職務と感情」髙中正彦=石田京子編『新時代の弁護士倫理』有斐閣,2020年12月,173–174頁
- “Social Distancing as a Public Good under the COVID-19 Pandemic,” Public Health 188: 51–53 (Co-authored with Susumu Cato, Kenji Ishida, Asei Ito, Kenneth Mori McElwain, and Masahiro Shoji, in press), doi.org/10.1016/j.puhe.2020.08.005, November, 2020.
- 「個人の危機と法制度:地域における法化と制度化の間隙」東大社研=中村尚史=玄田有史編『地域の危機・釜石の対応:多層化する構造』東京大学出版会,2020年6月,199–224頁
- 「民事裁判における自然人と法人:終局形態の一分析」社会科学研究71巻2号,2020年3月,131–153頁
- 「民事訴訟記録調査の概要」社会科学研究71巻2号,2020年3月,5–26頁
- 「民事訴訟の当事者に対するサーベイ調査:この20年の軌跡」法と社会研究5号,2020年3月,111–151頁
- 『危機対応の社会科学(下):未来への手応え』(東大社研・玄田有史・飯田 高編)東京大学出版会,2019年12月,408頁
- 『危機対応の社会科学(上):想定外を超えて』(東大社研・玄田有史・飯田 高編)東京大学出版会,2019年11月,362頁
- 「法社会学:『社会』を通じて法を捉えるために」南野森編『新版 法学の世界』日本評論社,2019年3月,154–163頁
- 「ルール適用の『融通性』」ダニエル・フット=太田勝造=濱野亮編『法の経験的社会科学の確立に向けて』信山社,2019年3月,359-381頁.
- 「防災対策が『わからない』:認知度から知る社会構造」東大社研=玄田有史=有田伸編『危機対応学:明日の災害に備えるために』勁草書房,2018年9月,109-138頁.
- 「日本における『成年』制度の成り立ちと社会的意義」ジュリスト1528号,2019年2月,78-83頁.
- 「人々の『信念』と法:The Republic of Beliefsとその周辺」東京大学法科大学院ローレビュー13号,2018年12月,28-43頁.
- 「ルールを破って育てる」論究ジュリスト27号,2018年11月,100-107頁.
- 「コメント:学際的研究のあり方を中心に」法社会学84号,2018年3月,136-141頁.
- 「立証責任の分配基準を求めて:法と経済学の視点から」伊藤滋夫編『基礎法学と要件事実』日本評論社,2018年3月,23–43頁.
- 「民泊に関する雑考:市場と法規制」法律時報89巻12号,2017年11月,1–3頁.
- 「数理モデルにおける法:規範と法」理論と方法62号,2017年9月,242–256頁.
- 「権利を生成する『社会』の力:理論に関する予備検討」上石圭一=大塚浩=武蔵勝宏=平山真理編『現代日本の法過程(下)』信山社,2017年5月,449–471頁.
- 「経済学は《法》をどう見るのか」法社会学83号,2017年3月,111-119頁.
- 「資源配分システムとしての『権利』の形成」法律時報89巻2号,2017年2月,19-25頁.
- "Motivations for Obeying and Breaking the Law: A Preliminary Study Focused on Labor Law and the Role of Non-Instrumental Motivations,"Japan Labor Review, Vol.13, Number 4, October 2016,pp. 28–46.
- 「判定をめぐって:スポーツにおける正確性と中立性」法学教室432号,2016年9月,60–66頁.
- 「社会規範と利他性:その発現形態について」社会科学研究, 67巻2号,2016年3月,23-48頁.
- 『法と社会科学をつなぐ』有斐閣,2016年2月,316頁.
- 「法律知識」山田昌弘=小林盾編『データで読む現代社会:ライフスタイルとライフコース』新曜社,2015年6月,138-143頁.
- 「法を守る動機と破る動機:規制と違法のいたちごっこに関する試論」日本労働研究雑誌57巻1号,2015年1月,15-25頁.
- 「法社会学:ちょっと斜めから眺める法の世界」南野森編『法学の世界』日本評論社,2013年3月,144-154頁.
- 「労働審判制度利用者の動機と期待」菅野和夫=仁田道夫=佐藤岩夫=水町勇一郎編著『労働審判制度の利用者調査:実証分析と提言』有斐閣,2013年3月,54-75頁.
- 「労働の法と経済学」日本労働研究雑誌54巻4号,2012年4月,72-75頁.
- 「法社会学」・「法と経済学」・「民事法概説」・「民法概説」越智啓太=藤田政博=渡邉和美編『法と心理学の事典』朝倉書店,2011年5月.
- 「当事者本人と代理人弁護士の認識の齟齬」ダニエル・フット=太田勝造編著『裁判経験と訴訟行動』東京大学出版会,2010年9月,169-186頁.
- 「社会ネットワーク分析の『法と経済学』への示唆」新世代法政策学研究6号,2010年4月,313-347頁.
- 「労働関係ネットワーク構築のための素描」水町勇一郎=連合総研編『労働法改革:参加による公正・効率社会の実現』日本経済新聞出版社,2010年2月,213-228頁.
- 「サンクションのない法の効果」太田勝造=ダニエル・フット=濱野亮=村山眞維編著『法社会学の新世代』有斐閣,2009年4月,251-281頁.
- 「環境問題の認知と情報的手法」アジア太平洋研究33号,2008年11月,1-20頁.
- 「経済学からのアプローチ」・「心理学からのアプローチ」森戸英幸=水町勇一郎編著『差別禁止法の新展開:ダイヴァーシティの実現を目指して』日本評論社,2008年9月,69-112頁.
- 「拡大する廃棄物市場と法制度:PETボトルと容器包装リサイクル法をめぐる議論を題材に」(片野洋平と共著)法社会学68号,2008年3月,189-211頁.
- 「雇用における性差別:法と経済学からのノート」嵩さやか=田中重人編『雇用・社会保障とジェンダー』東北大学出版会,2007年7月,199-215頁.
- 「暗黙の差別と法:経済学的アプローチと心理学的アプローチ」法律時報79巻3号,2007年3月,43-47頁.
- 「フォーカルポイントと法(1・2):法の表出機能の分析に向けて」成蹊法学63号,2006年3月,51-82頁;成蹊法学65号,2007年3月,91-128頁.
- 「法と経済学からの考察」水町勇一郎編『個人か集団か? 変わる労働と法』勁草書房,2006年10月,81-108頁.
- 「集合的サンクションに関する一考察」法社会学65号,2006年9月,8-21頁.
- 「差別の経済学的モデルについて」成蹊法学61号,2005年3月,115-141頁.
- 『<法と経済学>の社会規範論』勁草書房,2004年5月,195頁.
教育活動
| 東京大学大学院 法学政治学研究科総合法政専攻 | 「モデルで考える法と社会」 |
| 東京大学 法学部 | 「法と経済学」 |
| 一橋大学大学院 法学研究科 | 「法と経済学」 |
| 早稲田大学大学院 法務研究科 | 「法と経済学」 |
| 中央大学大学院 法務研究科 | 「法と経済学」 |
| 筑波大学大学院 ビジネス科学研究科 | 「法と経済学」 |