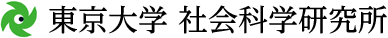案内
外部評価報告書
個別報告書
高畠 通敏
東京大学社会科学研究所 外部評価報告書
2000年2月22日
1 研究所が行っている全所的プロジエクトについて
社会科学研究所が、研究所として共通課題を設定し、全所的な共同研究を組んできていることは、法学、政治学、経済学などの分野を総合した社会科学研究所が設置されたその目的に照らして、妥当なものと考える。また、その共通課題の設定において、基本的に日本の社会の研究を中心にしてきたことは、日本の社会科学者による日本社会の研究を世界に発信するという意味において、また妥当であったと考える。実際、社会科学研究所がこれまで公刊してきた共同研究の成果は、その都度内外の学界の注目を浴び、高い評価をえてきた。この意味において、社会科学研究所は、その存立の意義を十分に示し、学界に大きな貢献を行ってきたということができる。以下に述べるのは、こういう成果を認めた上での望蜀の言である。
第一に、共同研究のテーマの設定の仕方は、もっとオープンであってもいいのではないだろうか。それぞれの時点において、どのように共同研究のテ-マを設定するか自体が大きな論議の対象の的となってよいし、また、そのテーマを解明するにあたっての視角や切り口も、もう一つの大きな問題たりうる。その意味で、共同研究の出発にあたって外部のメンバ-をふくめたシンポジウムなどを企画し、その内容を共同研究の成果とともに公刊することは 十分に考えられてよい。結果として、共同研究のありかたが研究所員の構成などによって制約されるのは止むをえないとしても、当初から便宜主義的に行われていないことを明確にする意味からも、これは必要だろう。(これは、とりわけ最近の共同研究である「20世紀システム」についていいうるように思われる。「20世紀システム」というジャーナリスティックだが学界内でははっきりとした合意のない概念をテーマとするということについて、また、一世紀間にわたる時代を課題とすることについて、多くの異論がありうるだろうが、それらをどのようなのりこえてテーマ設定が行われたのかは、読者には明確ではない)
第二に、共同研究の内容が、現実にはそれぞれの研究者の分担論文の集成という形をとるのは止むをえないとしても、その分担の仕方が動員された研究者の専門分野によるという便宜主義的な印象を与えざるをえない。その間隙に残された分野や問題は多い。従って、その分野を通観、展望して総合的に論じる序説あるいは結論の役割は大きい。その意味で、それぞれの個別研究を共同してまとめるという仕事に、もっと力を注いでほしい。
第三に、これは、社会科学研究所の設計自体にもかかわる問題だが、法律、政治、経済、労働などに比較して、他の分野については、手薄の感を免れない。残余の文化、宗教、教育、生活などの分野をひっくるめて「社会」という区分に押し込めるのは、研究所の名称にある「社会科学」ということの意味は何だろうかという問題に立ち戻ってもくる問題である。もし、社会科学研究所が今後も、はじめに挙げた分野を中心に運営されるとするなら、それは主題の設定の仕方に、当然、反映されなくてはならないだろう。そういう限定なしに主題を設定するなら、「社会」についての手薄感が生じるのも当然だろう。
第四に、この共同研究が、日本の問題について日本から海外に発信する本格的な共同研究たろうとするなら、数量的なデータの使用に関してもっと力を注ぐべきではないだろうか。海外では入手しにくい調査データや統計データを駆使する分析を行うことによって、社会科学研究所の共同研究はさらに海外の注目を集め、主題についてすべての研究者が最初に依拠すべき基礎研究としての地位を築くようになるのではないだろうか。
2 社会科学研究所の研究交流活動について
社会科学研究所は、対外的に開かれた研究交流の場として、重要な役割を果たしてきている。国内あるいは海外から社会科学研究所に留学し、研究所を基盤として一定期間研究活動をした研究者の数は、年々その厚みを増している。また、社会科学研究所は、アメリカ・ミシガンの国際的なコンソシアムと連携の下で、日本において行われた調査研究データの寄託を受け、それを他の研究者に利用させるデータ・コンソシアムとしての活動を開始している。今日、すべての大学は、多かれ少なかれ、こういう研究交流の場としての活動を行ってきているが、社会科学の分野でこれだけ大きな規模でこういう研究交流活動を行っているところはない。その意味で、社会科学研究所がはたしてきた役割は大きい。
しかし、こういう研究交流活動も、海外の一流の大学や研究所が行っている活動に比べれば、残念ながら見劣りがするといわざるをえない。それは、社会科学研究所が、社会科学の分野において国費で運営されている日本で唯一の研究所であるという点から考えると、ますますそうだといわざるをえない。
たとえば、研究所は、もっと多数の海外研究者、とりわけアジアの研究者を招いて、日本の研究者との共同研究を進めることもできるし、定期的に国際シンポジウムを開催して、日本の社会科学者に刺激をあたえることもできる。また、調査研究データの収集やそのオープンな利用に関しても、ミシガンの社会調査研究所のように、全国の若手の研究者を招くサマースクールを開催して、積極的に推進することもできる。あるいは、社会科学研究所自体が、統計数理研究所やNHK世論調査研究所が行っているような、日本社会に関する定期的継続調査を行い、学界の共通財産を形成してゆくことも考えられる。
こういう可能な研究交流活動あるいはオープンな研究センター的活動と対照して考えれば、社会科学研究所のこの面でも活動は、未だ十分とはいえない。
しかしそれは、基本的に社会科学研究所の財政的な制約から生じているとすべきだろう。
それは端的に、社会科学研究所の設備の貧困に表れている。海外から留学してきている若手の研究者たちの研究室は、私が大学視学委員として八年間視察し歩いた経験からしても、小さな地方国立大学や私立大学の大学院学生の研究室より狭く貧弱であり、到底、多くの国内・海外の研究者たちを胸を張って招けるという施設ではない。また、貴重な資料をたくさん抱えている図書館にしても、頭をかがめ身を竦めながらしか歩けない狭小さである。
この意味で、社会科学研究所が、その本来期待される役割をはたすためには、もっと大きな財政的な支援が与えられなくてはならないと考える。
3 社会科学研究所の組織について
社会科学研究所の組織の問題は、三つの側面から考えることができる。
第一に、研究所は、助手採用を通じて研究者養成の機能を担ってきた。助手は、戦後長い間、学部卒業者から直接、採用してきたが、近年では、修士過程を修了したものに移ってきている。戦後のこれまでの歴史のなかで、社会科学研究所の助手を経て、一人前の研究者として活躍するようになったものの数は多い。
しかし、こういう機能は、基本的に日本が未だに貧しく、大学院にゆけるものの数が限られていた時代に生まれたものである。近年、大学院を充実させ、それを研究者育成の基本的なコースとするようになってからは、研究所や学部が、大学院と並んで研究者育成の機能を担う必然性はなくなったと考えるべきだろう。また、一部の国立大学における講座制度にともなって自動的に助手のポストが配分されるシステムも、改革の矢面に立たされている。この意味で、社会科学研究所は、基本的に自立した研究者からなる組織として構成されるべきで、それに博士課程を修了し研究補助業務をこなす若手の研究者が、助手として付属するのが適切なのではないだろうか。
こういう観点に立てば、また、研究所が、三年ないし五年という有限の任期からなる所員を、共同研究の主題に即して全国あるいは全世界から招くということも、十分、考えられてよい。大学間の流動性が増大している状況に鑑みて、試みる価値がある制度だと考える。
第二は、分野別構成の問題である。研究所は、その設立の由来からして、主として法学部、経済学部の出身者を中心に構成されてきた。現在においても、東京大学のなかの社会・文化系の研究所は、アジアの地域研究に関して主として文学部出身者からなる東洋文化研究所、新聞やメディア研究に関して主として社会学部出身者からなる社会情報研究所というように、区分されている。
しかし、このような区分は、「現代日本社会」や「20世紀システム」の研究という主題に即してみれば、ほとんど意味をもたない。たとえ、学部間の人事的な垣根を一挙に取り払うことが難しいとしても、主題に即する、研究所間、学部間の人事交流は、もっと積極的に行われていいのではないだろうか。
この問題は、第三の問題、すなわち社会科学研究所の将来をどのように位置づけるかということと連動している。それは、いいかえれば社会科学研究所を、あくまで東京大学内部の付置研究所として考えるか、それとも、東京大学という枠をこえた国立の独立した研究所として位置づけるかという問題である。
社会科学研究所の大勢は、東京大学内の研究所という現状を維持することを志向しているように思われる。しかし、それは東京大学という特権的な大学の地位、そしてまた東京大学の教員に対する社会的に高い評価が、今後も長く維持されると考えることからくる錯覚ではないだろうか。
それは、社会科学研究所教員の地位を、東京大学のなかで学部教員に劣るものと一般に評価させてきたこととも、関係なしとしないだろう。東京大学のなかでは、学部から招かれて社会科学研究所を抜けることは普通であるが、その逆の例は、ほとんど聞かない。こういう慣習がつづいていることは、社会科学研究所が、本来、発揮すべき機能を阻害することにもつながっているのではないだろうか。こういう状況の下で国立大学の行政法人化が実現した場合、収入につながらない社会科学研究所がさらに冷遇されるだろうことは、容易に想像がつく。
今日、国立の独立の研究所で、社会的高い評価をえて活発な活動を展開しているものは、数多くある。社会科学研究所が、日本で唯一の国立の社会科学研究所として、東京大学の枠を離れて大きく飛躍することを検討課題とすることは、十分意味あることだと考える。