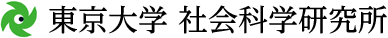案内
- トップ
- 外部評価報告書
- 付属文書1. 全所的プロジェクト研究についての専門家パネル
- 3. 専門家パネルの座談会の速記録
外部評価報告書
<提出資料> 付属文書1. 全所的プロジェクト研究についての専門家パネル
3. 専門家パネルの座談会の速記録
出席者(発言者)
|
●編集・出版関係者 伊東 晋氏 有斐閣編集部 |
●社会科学研究所 廣渡清吾所長 |
司会(末廣) きょうは雨の中をおいでいただきましてありがとうございます。最初に所長より挨拶と外部評価についてのこの座談会の位置づけをやっていただいて、その後私から趣旨説明をいたします。そのあと全体研究会の研究事務担当の土田さんから、すでにお配りしてある全体研究会の過去の簡単な経緯をお話しし、それから皆さんのお話に入っていきます。できるだけ自由に、かつ率直な意見を出していただくのが目的ですので、よろしくお願いいたします。
ではまず所長からお願いいたします。
廣渡 社会科学研究所の廣渡です。この座談会はこういう背景があってお願いしたということを、最初に私から簡単にご紹介させていただきます。
ご承知のように、昨年の11月に大学審議会が21世紀の大学像の答申を出し、学術審議会は日本の学術体制についての答申を準備しています。いずれにしても21世紀を目指して日本の高等学術研究体制をどうするかという政府サイドのいろいろな見通しが発表されているところです。かねがね大学、とくに研究機関については、リサーチアセスメント、つまり外部からの研究活動その他についての評価が必要であると要請されています。
国立大学の附置研究所というのは、自然系、文系合わせて全国に66あるのですが、十いくつかある文系の付置研究所はほとんど外部評価を行っていまして、たぶん社研がラストランナーだと思います。
外部評価については、部分的なある特定の部門についてだけ公開して、そこを評価してもらうという方法、特定の計画を持っている場合にその計画をその場所で実現することが適切かどうか外部に評価を頼むという場合等々いろいろなケースがあります。
社研の場合は全部をとにかく見せて、社研の全体についてアセスメントをもらおうということを考えまして、したがって評価の項目は研究所の研究体制そのもの、それから研究所のプロジェクト研究のあり方、研究所の国際的な役割、大学院教育への参加の仕方、研究所の人事制度のあり方、それから91年に設置された附属の日本社会研究情報センターのセンターの活動、それから最後に、そういう現状を踏まえて、将来私たちは何を研究所の未来像として考えているかということを含めて、外部の方の意見を聞こうということにしました。
その中の重要な個別の評価項目としてプロジェクト研究のあり方というのがあります。外部評価委員は、2枚目の紙にあります8人の方にお願いをして、承諾をいただいています。国内で5人、国外で3人、都合8人の委員の方々です。専門は社会科学研究所のスタッフの専門に合わせてバラエティーに富ませてあります。
きょう皆さんに末廣のほうからお願いをしてここに来ていただいた趣旨は、社研のプロジェクト研究のあり方についての率直なご意見をいただいて、そのいただいたご意見を私たちのほうで整理をして、この8人の外部評価委員の方々に最終的な外部評価の資料として提出させていただきたいということです。
外部評価委員は全面的にいろいろなところを見なくてはいけませんので、個別に突っ込んで個々の項目に立ち至って調査をするということはなかなか難しいので、プロジェクト研究とセンターについてだけはこのような専門家パネルを実施して、そこで突っ込んだ具体的な意見をいただいて、それを外部評価委員会に提出して、それを踏まえてアセスをいただこうということにしています。
全体として今年度中に最終的な外部評価報告書を評価委員会からいただくというスケジュールで進めたいと思っています。したがってきょういただくさまざまなご意見、評価というものは、最終的には今年度末に外部評価委員会の報告に結実することになる。最後に外部評価委員会の報告が作成されましたら、ぜひ皆さんのほうにもそれをお届けしたいと思っています。
そういう枠組みの中できょうのお集まりをお願いしましたので、忌憚のないご意見、評価をいただければ大変ありがたいと思います。
司会 それでは座談会を具体的に始めたいと思います。私のほうから簡単な趣旨説明をした後、土田さんから経緯説明をし、それから4、5分ずつ皆さんにご意見をいただく。その後は自由に意見が交錯しながら新しい問題が出てくるというかたちで、どんどん相互に話をキャッチボールのようにしていただいたほうがこちらも参考になります。
それから、これは座談会の記録をまとめて、ストーリーのある読みものとして残すのが目的ではありません。皆さんの率直な意見が外部評価委員、もしくはわれわれの今後の運営に生かされるということに重点を置いていますので、連続性とか整合性とかいうことはあまり考えていただかなくて、直接忌憚のない意見をお願いしたいと思います。
今回の専門家パネルと呼ぶ全体研究会の評価は、当初は何人かの、外国人と日本人の研究者に『現代日本社会』全7巻と『20世紀システム』全6巻を読んでいただこうと思ったのですが、これを全部まとめてその研究の意味は何なのかということをお願いしても非常に難しい。それともう一つは、このシリーズについてはすでに毎回合評会、つまり各関係の研究者に来ていただいて意見を聞いていますので、こちらとしては出版、編集の担当の人に、研究所が共同研究をやり、企画から最後にシリーズものの編集に至るまでやるというやり方についての意味と問題点を自由に出していただきたいということで、5人の出版、編集の方々に参加していただいたわけです。
そこで、まず皆さんにご意見を伺いたいのは、シリーズものの企画・編集については、出版者側がイニシアティブを取ってやる場合があります。この場合はいろいろな研究者を含めて相談しながら企画を立てていく。それから研究者が個々に参加し、その研究者がイニシアティブを取ってシリーズを作っていく場合もあると思います。また、たとえば学会がイニシアティブを取り、それを出版者に企画として持ち込、学会主導のケースもあると思います。
この研究所の場合の特徴は、常に研究所の名前を付してシリーズものを出す。それが全体研究、現在は研究所プロジェクト研究と呼んでいますが、共同研究の成果で、同時にこの研究所の公的な仕事と位置づけられています。では公費を使って研究所がこういうかたちのシリーズものを時間をかけて出すことの意義は、編集者の立場からどこまで評価していただけるのか。あるいは問題があるならそれを出していただければと思います。
研究所主導というけれども、多くの場合はやはり特定の個人のイニシアティブはどうしても必要である。たとえば『現代日本社会』で言うと、馬場宏二先生の会社主義というキーワードがあったし、今回の『20世紀システム』は橋本寿朗さんの「20世紀システム」、もしくは藤原帰一さんの「戦争と市場の管理」などがあります。
ところがある程度個人のイニシアティブでありながら、同時にそれが研究所全体の研究のアイディアもしくは発意としてまとめていかなければならない。結局研究所が存続していくためには、研究所としてでなければできない共同研究のあり方と、そしてその成果の還元としてこういうシリーズものを出すというところに行きつく。たとえば学部の教官は授業を持ちながら、同時にいろいろな企画を出して本をまとめることも可能だし、出版社、編集者のアイディアで、これぞと思う執筆者を集めてシリーズを企画することも可能です。そうするとこういう国立大学の附置研究所がレーゾンデートルを問われたときに、どういうかたちの共同研究と、その出版もしくは成果の還元の仕方があるのかというところにどうしても行きついてしまう。
今後社研の共同研究をどのようにやっていくか、我々自身もいま検討を始めていますので、できるだけ率直なご意見をいただければと思っています。では土田さんから、お配りした資料を含めて、流れを簡単にお願いしたいと思います。
土田 全体研究と呼ばれる共同研究のプロトタイプは、社研の15周年のころからすでに表れ始めていますが、一応いまのようなかたちの全所的な共同研究と言えるものは、基本的人権の研究から始まりました。1964年から『基本的人権の研究』始まりまして、次が『戦後改革』、『ファシズム期の国家と社会』、『福祉国家の研究』、そのフォローアップとしての『転換期の福祉国家』、そして『現代日本社会』が来まして、いちばん最近の『20世紀システム』と、これだけ重ねてきています。 この全所的な共同研究というのは、テーマの設定からまず所員で議論をしまして、数人の運営委員を選んで、定例の研究会を重ねていきます。研究会の他に運営委員会でも中味を固めていく議論をして、数年の後には6冊から8冊のシリーズで書物を刊行するというルールになっています。
資料にありますように、それぞれのプロジェクトの期間は、『転換期の福祉国家』はフォローアップとして非常に短期で行われたのですが、『基本的人権』が6年、『戦後改革』は6年1か月、『ファシズム』が7年1か月、『福祉国家』が6年、『転換期』3年、『現代日本社会』6年8か月、『20世紀システム』が6年、準備から成果の完結までの時間がこれだけかかっています。
テーマは社研に在籍する法律、政治、経済のどの専門からも参加できるものが選ばれて、一つのテーマにさまざまな方向からアプローチするかたちで行われています。そして一応社研の特徴と言われてきた比較、総合、実証を旨とした分析であるということが条件になっています。比較というのは、社研には外国研究者も従来からたくさんいまして、現在ではヨーロッパ、アメリカのみならず、アジア研究の方も多いですし、それと日本研究の人も含めて、比較の視点から対象を見るということです。総合というのは、この場合たくさんの専門からインターディシプリナリーに研究し議論を重ねていくことを、従来総合と言ってきました。それから実証的な研究であること、もう一つ、歴史的な視点を持ったものであることも、重視されて進められてきました。
成果が数冊のシリーズとして刊行されますと、主として所外の方をお招きして合評会を行って、それをまた原則として紀要に載せます。合評会での評価のほかに、世間の評価と言いますと、売れ行きとか、雑誌や新聞の書評などに出たりしますけれども、出版の世界の状況とか世の中の動きによって売れ行きはかなり違ってきますので、これは難しいところです。必ずしも、学会へのインパクトや、長く価値の変わらない業績、このテーマを研究するにはあのシリーズを素通りしては語れないとかいった評価と、売れ行きの多寡が一致するわけでもありません。最近の『福祉国家』と『現代日本社会』と『20世紀システム』については実売数の資料をお送りしておいたと思いますが、あくまでも評価の指標の一部であると言うことです。
『現代日本社会』の場合には、先ほど末廣先生がおっしゃったように、議論の過程でキーワードがいくつか出ました。会社主義とか、政治の拡散とか、それから日本経済がちょうど一人勝ちの時期でしたので、これは反語的に言われたのですが、日本はモデルたりうるか、などが出されました。会社主義というのは簡潔でキャッチィーでしたので、広まりまして、マスコミのほうでもある程度定着したと思います。
『20世紀システム』の場合には、いままでと比較した特徴を言いますと、システムという概念を採用することで、単線的な発展史観を、それまでも徐々に脱却しつつあったのですが、完全に脱却した。それから自己言及性とまで言うとちょっと言い過ぎですが、対象を認識する学問と、それを踏まえて作られる制度が現実の変容を促すし、またそれが認識の仕方にもフィードバックされることとか、社会主義とその影響に関しては、イメージと現実の相互浸透性ということも言われていまして、これは従来の社研の研究にはなかったことでした。
本の作り方としても、『現代日本社会』のころから、運営委員会でまとめた序論を最初に載せて、全体の考え方をそこで明らかにするようにしました。各巻にも序論がついています。
『20世紀システム』はその序論をさらに執筆期間の直前に執筆者全員に配りまして、なるべく議論のかみ合うものを目指しました。それから最後に運営委員による後書きをつけて、いわば顔の見える編集を目指した。黒田さんが運営委員と相談しつつ、索引も作ってつけました。
そういうふうに運営の仕方も、本の作り方としても、内容としても、一応進化しているわけですが、先ほど所長や末廣先生のお話にもありましたように、社会も、大学も、研究所も非常に揺れ動いていて、いわば効率が求められる時代になってきています。共同研究のテーマの大きさとしても一種行きつくところまで行きついているとか、大人数で数年かけてやることに大変エネルギー、コストがかかるということとか、それから社研は、国際交流など多くの仕事をかかえていまして、非常に忙しい状態にあるとか、あるいはSSJフォーラムとかニューズレターなど、ほかの発信も並行してやっているということで、現在この共同研究をどのようなかたちでこれから考えていくのかというのが議論されている、というのが最近の状況です。
司会 お配りした資料にありますように、『現代日本社会』も『20世紀システム』も研究費として2000万というかなり大きな金額を使っている。それから結果的にはスタッフのほぼ全員に近い人が参加している。かつ6年をかける。これがいいのか悪いのかは現代の状況の中で判断が分かれるところだと思いますが、それを含めて伊東さんから順番に話をしていただいて、それぞれ出された問題をまた引き継ぐかたちでどんどん議論を出して下さい。
最大の趣旨は、過去を振り返ることではなくて、あるいは過去の業績がよかった悪かったの評価ではなくて、未来に向けてどうこれまでの経験を生かすか。そこにあたって出版・編集者の皆さんのお知恵を生かしたいということですので、ぜひそこの点を念頭に置いてご発言いただければありがたいと思います。では伊東さんからお願いします。
伊東 基本的には出版社でできることと、研究所がいまやっておられるような、企画から刊行までずっとコミットされるというやり方とは、一種の棲み分けがあるのではないかということに尽きています。逆に言うと、出版社でもできることについては無理にやらなくてもいいということになるのですが、一つは、出版社で企画する場合、多くの場合は商売ですので、最終的にできあがる本の読者とか、執筆のスタイルとか、執筆者の分野とか方法を最初に限定して、つまりできあがったイメージを先に作っておいて、そこへ向けて本を作っていくというやり方をして、言ってみればリスクを消したり、あるいは経済的な意味での収益を大きくしたりしようとすると思います。
研究所の場合はまだ不定形というか、テーマ自体を探しながら、しだいにアウトプットを作っていくというやり方ですね。これは大きな新聞社とか大きな出版社の場合は可能でも、日本にあるほとんどの出版社にとっては相当難しいことで、それは公的な研究機関、あるいは大きな研究機関のやり方だと思います。
その結果を商業出版というかたちにするかどうかというのはまた別の問題で、必ずしも出版というかたちでの社会還元だけが還元ではないと思います。ですからやはり基礎的な研究ということをお考えになればいいのではないかと思います。
たとえば社研の例にあるような、研究期間に投じられる研究費が2000万円という規模のものは、われわれの規模の出版社ですとほとんど考えられない金額で、そういう意味では全くタイプが違う。期間という面で見ても、たとえば私のところで本を作る場合、社内で一応の了解を取ってから刊行開始に至るまで4、5年かかると、それを担当する編集者は相当きつい。ずっとそれについて関心を持続しなければいけないとか、それから社内で活動するときの正統性というか権威づけを絶えず会社から与えてもらっていないといけないとかいうことがありますので、長期というのも通常の規模の出版社だときついわけです。
そういう意味でも、研究所がそういう研究スタイルを維持し、成果を問うというのは重要なことです。『20世紀システム』にしても、『現代日本社会』にしても、私などが考える社研で作る本のスタイルの典型的なものかなという感じもします。
司会 では次に増山さんお願いできますか。増山さんもいろいろな新しい経済学シリーズとか企画されておられますので。
増山 私の所属する出版社では、社研のシリーズに近いものだと『シリーズ現代経済研究』というエンドレスの研究叢書を出しています。これはもともとクオータリーで出していた雑誌で『現代経済』というのがあったのですが、会社方針でやめてしまったところ、アカデミズムのほうから非難があがりまして、なんとか継続したいということで、雑誌よりも不定期に、学者のいろいろな意見と、現代日本で起こっている経済的な直近の関心をマッチングさせたところをテーマにして出すことになりました。あまり期間を区切らずに集まって議論して、それを本にまとめています。年に3冊たて続けに出ることもあれば、1年半ぐらい空いてしまうこともありますが、今9年間で17冊ですから、平均すれば1年に2冊見当で出しています。
編集部の経済を担当している人間と、コアメンバーになってくださる大学の研究者の方々とで、現代経済研究グループを作りまして、2ヶ月に1回研究会をやります。交通費などお金は一切出していません。とにかく集まって議論して、いま問題なのは何かという話から、かなり激しい議論をします。コアメンバーはいま10人ですが、常に設定した会議の日に全員が来るとは限らず、実質的にはわれわれ事務局3名を入れて8人~9人ぐらいで議論をして、そこでテーマがいろいろ上がってきます。テーマが決まると、だいたい提案者のような人がそのテーマのエディターとして立って、基本的な構想、章立てをどれぐらいにするか、各章はどんな内容にするかなど決めていきます。できれば執筆者の案までを出してもらいます。次の会議でそれらをエディターに発表してもらって、ほかの方々と素案をつき合わせます。最近ではEメールがありますので、会議の事前に案件をメールで流して、会議に集まったときにはいちいち議論せずに、すぐに共通了解ができるようなシステムにしています。
われわれ事務局のほうも、執筆者の選定や中味に関わる事柄までかなり口をはさみまして、オーケーが出ますと、企画書を書いて会社の中で企画を通します。同時にエディターのほうは、執筆依頼の手紙と本の趣旨をレポートにして送って、快諾を得た方に、分量・論文テーマ、締め切り等を打診して、ある程度決まったら、3か月後ぐらいに一回ペーパーを出し合ってミニカンファレンスを開きます。そこでまた相当もみます。もむと問題点がはっきりしますので、改訂稿が出て、それをベースに最終的に本にします。第2草稿があまり良くないとエディターがその人と直接話したり、あるいはわれわれがかなり負担を強いられる場合もあります。
期間としては、カンファレンスを1回ないし2回やったり、本の制作期間なども含めて、だいたい1冊につき半年から1年ぐらい見る。1年以上たってしまうと、設定したテーマ自体が微妙に過去のものになってしまいますので、そういう状況にはしない。あるいは逆に、時事的なことに惑わされない普遍的なテーマをがっちりとやるとか、ヒストリカルなテーマをやる場合もある。『現在日本経済システムの源流』などはいつ読んでも大丈夫なものとして出したし、逆に、あと2年後の何月には何が起こるかなどが明らかなとき、たとえばEC統合とか、新農基法実施などのときには、時期を合わせて議論を沸騰させ注目を浴びることをねらって、そこに向けてプロジェクトを組むというような中期的なものもやります。
基本的には時間を長くかけてしまうと、さまざまな問題が生じます。執筆者が自分の研究テーマを変えてしまったとか、留学してしまうとかという問題、それからテーマがアウト・オブ・デートになってしまう、あるいは突然世界潮流が大きく変わってしまう、たとえば絶好調といわれていたアジア経済が突如(?)危機的状況になったりすると、ものによってはそれまで議論してきた基本的な論調では意味がなくなるなどのケースです。編集者側では、人事異動の問題と、1冊のテーマにずっと縛りつけられることによるさまざまな問題があります。それから営業的な問題。シリーズとしたら、完結しないとなかなか売りにくいとか、巻と巻の出るあいだが空き過ぎてしまうと、書店に忘れられてしまうなどといったことがあります。それで先程いったようにだいたい年に2冊ペースを目安にやるということを努力目標にしているのです。
司会 どうもありがとうございました。次に、『世界』の編集をやっておられる馬場さんから。
馬場 ぼくはこの数年雑誌の編集に重点的に携わっていますけれども、その前は単行本のセクションにいまして、講座・シリーズ等を少し手掛けたこともあるので、本を作る側の立場と、半分ジャーナリズムの世界に足を突っ込んでいる者の立場から話をしたいと思います。
いま伊東さんや増山さんがおっしゃった出版社が本を作る場合の基礎的な条件はだいたい小社も同じです。シリーズものというと、まず岩波講座と言われるもの、もう少しアクチュアルな要請に応えるシリーズ、個人の書き下ろしを集めた叢書、など三つぐらいのシリーズ企画の形態があるわけです。叢書は講座の副産物的な性格のもので、講座の執筆者でこれと思う人を別に1本釣りでお願いして、1人1冊書き下ろしにするというシリーズです。 これまで「世界歴史」とか、「日本歴史」とか、いわゆる岩波講座の看板は、学会のオーソリティーというか、いまの時点でまず間違いないと言われるような定説を通説として提示し、それを広く一般読者に知らしめるという機能があったと思います。そういった啓蒙性はいまでも強く残ってはいますが、学会のシステムというか、ポリティックスというか、そういったものがかなり大きく変わってきていますので、学会のヒエラルキーをそっくりそのまま取ってきて、パッケージにして講座にするというかたちでは、読者に対するインパクトが弱くなってきています。最近は、よく言えば学際的、あるいは学会の枠に縛られない、あるいは問題先行型の、家族の問題を考えるとか、文化のあり方を考えるとかいったシリーズが少しずつ増えてきている傾向にあると思います。
今回、『現代日本社会』、『20世紀システム』という二つのものをざっと読ませていただいて、テーマ設定に関しては文句のつけようがない。非常にワイドで、ジェネラルで、しかもニュートラルなテーマ設定で、しかもある種の現代性を強く意識しています。しかし出版社だと、本を作るまでに長い時間をかけられないということもありますし、市場性をより強く意識しなければいけませんので、もう少しアクチュアルな短期的な問題を据えることになりがちだと思います。
ただ、現代の日本社会にしても、20世紀という世界システムにしても、現代という時代や社会を読み取るパラダイムの発見や切り口をはっきりさせる戦略もあり得ると思います。もちろん射程は20世紀の 100年間とか、あるいは全世界ということでもいいのですが、そういったある種の問題をむしろ見つけていくというかたちで明示的に提示し、そこに社研の問題意識とか視角のユニークさを大いに発揮するような打ち出し方も考えられるのではないかという気がしました。
社会的ニーズということに関して難しいのは、どのあたりの層をを指して社会というかという問題です。(部数が『現代日本社会』で7000部とか、『20世紀システム』で4000部近く売れています。これだけ売れたから十分社会的ニーズを果たしているのではないかという気もするのですが)。社会的ニーズというときの社会は書籍を購読する一般読者のことを言うのか、あるいは論壇的なものを言うのか、あるいはアカデミズムを言うのか、政策決定者とか行政の担当者まで考えるのか。そのへんのターゲットがいま一つ見えにくいような気がしました。ターゲットをどこに絞るかによって、研究のコンセプトや本の編集のあり方も大いに違ってくると思います。
政策決定者云々ということを言うと違和感があるかもしれませんが、社会科学は社会に対するある種の批判者として、時の社会や現実政治にコミットする姿勢が本来あったのではないか。社研が戦後できた経緯は、おそらくそのあたりがかなり強く意識されていたのではないかと思うのですが、こうして『現代日本社会』とか『20世紀システム』を見ますと、そういう社会科学の姿勢が、一般読者に対しても、政策決定者に対しても、いずれにしてもちょっと距離が置かれているという印象がどうしてもぬぐえない感じがしました。
長期的に6年かけて、あるいは2000万円という投資をしてこれだけのシリーズを出すのは出版社には非常に難しいですが、社研のように研究の期間をじっくり寝かせて、執筆期間を置いて、出来たものから回し読みをして討議をして、全体のレベルを高めて、しかもテーマの射程を広げていくという姿勢に関しては、共同研究の良さとして、非常に大切なことだと思います。出版社はいま不況の中で自転車操業状態で、すぐに本にしなければという強迫観念がありますので、それは学ぶべきことだと思います。また刊行後に合評会を開いて外部の反応を聞いて、反省と研鑽のフィードバックを行っていくということも、なおざりにされがちですが重要なことです。
われわれが本を作る場合、最近の傾向として学際的とうたって面白さを強調したり、従来の権威主義的なものとは違う、と何か奇想天外な読後感を予感させたりしがちですが、いいながらも、結局内外のチェック機能が働かずに、執筆者が一種野放し状態になってしまうということがありうる。玉石混交で、いったい何にアクセントがあるのか、何を訴えたいのかわからないようなものが結果として出来てしまうということになりかねないわけです。
そういう意味では、もちろん社研のこのシリーズは、学際的ということはうたっていますけれども、しかしやはり社会科学というところに踏みとどまって、現代日本とか20世紀というようなアクチュアルな問題について、そのディシプリンの範囲で何を応えうるかというアカデミズムの本来の姿勢が保たれています。
また、序論や後書きをつける、あるいは索引をつけるなど、ある種の読者サービスを図り、顔の見える編集物という工夫をなさっていることはたしかによくわかります。しかしもう一つなぜこういう本になったのかというプロセスを、たとえば月報とか、座談会とか、付録など何らかのかたちで本体に組み込むなど、討議の果てにそういった各論文の結論に至ったプロセスに少しでも読者が参加できるような、どこかにそういう編集上の工夫の余地があるのではないかと思いました。
司会 ありがとうございました。いろいろ出していただきました。では次に同文館の勝さんお願いします。
勝 いま商業出版という私たちのサイドでは、現実の出版不況の中で、どれくらいの時間をかけてどういう企画を立てて、そこにどれだけコストを投入して、人的コストもですが、それでいったい何が作り出せるかという問題が一つあると思います
その問題と、実際いい企画が立てられるかどうかというのはまた別の話ですが、そのあいだで編集者なり営業なりは、実際のところかなり苦労しているところがあると思います。
長期的に何かを考えて1点の企画でも作りあげるといった余裕が、現実の出版社ではかなり無くなってきている。うちなどは営業も含めて全部で20人ですから、規模からいったら非常に小さいほうです。やはり大きい出版社のほうがシリーズものとか講座ものでも、ある程度人を割くことができますし、そこそこのテーマを設定すれば、つくることができる。うちのように7人か8人の編集者で、しかも分野もある程度広くカヴァーしているところにとっては、講座を作るということ自体かなり難しい。きょういくつか資料をいただいていますが、金額なども数年の合計では前回の『現代日本社会』と今回の『20世紀システム』は2000万以上の高額のお金を投入している。ではひるがえって、私たち出版社が、そういうお金と人をある程度割けるという前提が仮にあったとして、同じものができるかどうかはまた難しい問題があるだろうと思いますが・・・。
『現代日本社会』の1巻目は別格としても、『20世紀システム』にしても、論文集的な形態か、共同討議のもとにできた本であるかは問わないとしても、3000部売れているというのは、やはりこの時代としては売れていると思わざるをえない。
ただ私から見ると、たとえば岩波書店の『開発と文化』などの講座ものと『20世紀システム』などとは結構執筆者が重なっていたりする。これでは社会科学研究所が共同研究の成果として作った本だから買う、という人はあまりいないのではないか。研究所がこういうことをやっているという一つの証として本の形態が必要だということなのか、それとも本というかたちに最終的に仕上げて、そこで社研をアイデンティファイさせるということが目的で、プロジェクトなども設定せざるをえないという状況になっているのか。何回もプロジェクトが行われていますから、どこかの時点で転換期もあったと思います。そのへんから研究所のスタイルを問い直していくということが、社研に限らず、必要な時期に差し掛かっているのではないか。
もう一つは、社会科学というものをどう考えるかという学問の問題です。これがいろいろな意味で転換期に差し掛かってきていて、だからこそ私たち出版社のサイドでもどういう企画を練ったらいいのかわからなくなってきている。これは社会科学に限らず、歴史、人文の分野もそうかもしれないのですが、歴史、人文というのは、比較的長いこと著者などと話をして考えながらかたちにしていって、企画を立てた時点と刊行する時期の間にある程度時間があっても大丈夫という側面はあると思います。社会科学の場合はそういうものもあるけれども、そうでない時々のテーマがここのところ急速に変わりつつある。
司会 馬場さんがいま言ったのは政策科学と批判科学の統合ですね。以前は政策科学に対して批判科学というふうに並べていたのが、先ほどのご発言はそれを統合したようなかたちでの提案があってもいいのではないかという言い方ですね。勝さんの場合の社会科学というのは、もうちょっと言うと何ですか。
勝 政策科学と批判科学の統合も必要かもしれませんが、いろいろな時代的な状況に社会科学が振り回されすぎているのではないかという一般的な感想があるわけです。さまざまな概念が次から次へと言葉として先行してくる。問題は、そういった言葉が定着してくると、みんなそれをわかったような気持ちになってしまうという現状があって、それに対して社会科学における批判的な部分をどうバランスを取りながら出していくのか。これはかなり難しいことだけれども、研究所にはそれを出しうる方法や仕方があるのではないかと思うんです。そのへんは言うはやすし、行うはがたしというところがあって、もちろん私たち出版サイドの責任も大きいと思います。
本の作り方としては、6巻とか7巻で出すだけではなくて、共同討議のプロセスみたいなものとか、テーマをどう決めていくのかという準備段階とか、プロセスの議論を通して最終的にこういうテーマが決まったとか、あるいはサブとしてどういうテーマがありうるかという討議を、むしろ本のかたちにするとかね。
司会 先ほど馬場さんは月報という言い方をしていたけれども。
勝 たとえばものすごく大変だと思いますが、全6巻の他に1巻作って、全員にチャプターなり、節なり、あるいは項目なりを割り当てて、「20世紀」というテーマでこれを打ち出したいというものについて全員が草稿を書く。それをまた全員が読んでそれぞれにコメント・赤字を入れて、それをもう一回書き直すということで、どの章にも全員が責任を負うぐらいの気持ちで何か1巻作ってみる。そうした本で問題提起をして社会的にアピールする。これは通常の出版社では出来ないことですので、そういうかたちで労力をかけるという方法はありうると思います。
司会 コアメンバー主義ですね。コアメンバーと事務局がかなりがんばってやって、それをEメールで交換するのではなくて、それをもっと全員参加型に持っていくということですね。
]勝 それを公開する。きついな。(笑)とにかく思い切ったことを考えていかないと、社会科学にしてもいろいろな意味で行き詰まりがあるし、そういう中でなんとか出版社サイドの人間も新しい企画なり、あるいは業界の中で一種のすみ分けみたいなことを含めて、いろいろな先生方をつかまえてコアメンバーを作って、こういうことを打ち出そうとかいうことを実際にはやっているという状況もあるかと思います。
そうした中で研究所の役割をどういうふうに出すか。研究所だから非常にうらやましいという面もあるけれども、結果としてできあがった本は論文集に近いようなイメージを与えてしまう。これはかえってマイナスなのではないかという気がします。資料を見ると5年間でこれだけのお金をかけて40回、50回と研究会をやれば、膨大な時間とコストです。それでできあがったものが、結果としてはそれだけ労力をかけたものなんだということが正直言ってわからないわけです。
司会 共同研究のプロセスを示す資料をもしも各巻に入れて読者に回したら、「頭おかしいんじゃないの?」と言われたりして・・・・。(笑)
勝 たとえば私は、個人的には末廣先生とは前からお付き合いがあって、岩波で出ている『開発と文化』の論文を読ませていただいて、これはいつも議論していることだな、と。そうして『20世紀システム』の中の末廣さんの論文を読むと、いつも議論していることが、今度はこうなったのかな、というぐらいのイメージしか実際のところわかない。それを脱却するようなかたちで、社会科学研究所ということとそれぞれの執筆者の個性なり特徴の両方を、うまく出していくための方法はどういうことがありうるのか。この点がかなり深刻な問題で、それでこの場に呼ばれているのかなという気もしないでもない。
ただ、あまりその点を出版社の人間が突き過ぎてしまうと、ではいまの出版社の状況は、極端な話、お金さえつけば何でも本になるとか、あるいは出版不況といっても、専門図書の点数自体は以前に比べてどんどん増えていて、しかも返品率はそれに輪をかけて年々増えている。そうした状況を外部の機関が見れば、出版社サイドは何をやっているんだと逆に突かれかねないという問題があって、ですからこのへんでやめておいたほうがいいのかもしれません。(笑)
司会 それはまた後で。次は『20世紀システム』を実際に編集して一緒にやった黒田さんですが、きょうはこの本の編集者ではなくて、むしろ一若手編集者として自由に発言していただければと思います。
黒田 6年間ぐらいの長期にかけて研究するということ自体たしかにすごいことで、お金もかかる。ただ、これは別に社研の専売特許ではなくて、東大出版会の場合、東京経済研究センターという経済学者中心のカンファレンス・ボリュームなどを編集して本を出していて、その場合も最初の構想から始まって4年ないし5年という期間がかかっています。そのようなかたちで学術的な成果を出していくというのが、社研の共同研究に限らず一つの形態としてありうる。出来たものもそれなりの社会的ニーズというか読者層をきちんと設定することができていると思います。
座談会みたいなかたちで議論のプロセスが読者に見えるようなかたちとおっしゃいましたが、第6巻合評会の刀弥館さんのプレゼンテーションの部分の文章を読ませていただくと、それと同じようなことを言われていて、たしかによくわかることなのですが、本当に読者にとってそれが必要なのかどうか。
社研の全体の共同研究というスタイルについてぼく個人の関心から言えば、一般的な読者というか、刀弥館さんが、「だから何なんだ」ということが知りたいとおっしゃっていますが、そこに別におもねる必要はない。それに対する答えで藤原先生がおっしゃったように、「こうして、こうなって、こうなった」という事実の解釈をきちんと提示していくという、学問本来のあり方が基本だと思います。そのうえで「だから何なんだ」という疑問を背景にしつつ、読者に提示していくわけです。
たとえば部数で言えば1万部とか8000部とかいうところを想定するようなことは一切考えないで、3000部なら3000部、2000部なら2000部という、コアは専門的な読者で、そこにしっかりと売れていくという意識でプロジェクトというか本を作ったほうが基本的には成功なのではないか。
その意味では『現代日本社会』は売れ過ぎたと若干思ったりもします。その残像があって『20世紀システム』が売れているか売れていないかの評価をするのは難しいところですが、基本的には上に言ったようなことを考えています。たとえば2巻のアメリカの経済成長の巻は、主としてすごくミクロな細かい話です。売れ行き自体は2000部確実に売れて、なおかつゼミなどでかなり使われているという現状を考えた場合に、部数的には、『現代日本社会』より少ないですが、確実に受け入れられているということで言えば、非常に成功なのではないかと思っています。開発主義についても同様です。
別に社研のシリーズだから、新しいテーマだからといって特別に扱われるわけではなくて、書店には一般の本と並べて置かれるわけですから、たしかに見た目とか、装丁とか、価格設定とか、外身の部分、読者がキャッチしてくれる部分については意識するけれども、中身については、読者を限定してきちんと押さえたほうが、本の成り立ち方としてはいい方向に行く。一般読者に非常に広く受けるかどうかは、東大出版会としてはという限定付きになるのかもしれませんけれども、あまり欲張らないようにしています。
伊東さんの作られたメモの中で、対象把握、ニーズとつなぐためには、特定のディシプリンか特別の方法での切り口か、というところがありますが、社研の共同研究を組織してやる場合には、ディシプリンの大切さというか基本線を読者にきっちりとアピールするような方法を取るのが、やり方としてもたぶん間違いがないでしょうし、しっかりしたものができるのではないでしょうか。
その場合、全所的に全員参加するかどうかは別で、テーマによっては学外の方を組織して、社研自体はプロデューサー的な中心になってテーマを企画していくというやり方がいいかもしれません。
最後に、今回のこの座談会自体が外部評価ということですが、外部とか世間というのをどこに設定して考えているのかということを、東大出版会としても、学術出版を出している者としても考えてみたい。
これは本当に対照的で、刀弥館さんの文章を読んでいて非常に面白かったのですが、当然こういう考え方はあるだろうと、一読者としてはよくわかるんです。しかし結局読者のニーズに応えるような、先程の話で問題提起的といわれましたが、そういうものを作ろうとなると、全く別の編集の仕方、運営委員会を組織して班ごとに研究会を重ねて、最後に原稿をまとめるといういまの方式ではなくて、別な発想で企画の成り立ちから変えないと、そういう本はできない。もしそういう世間のニーズがあって社研の役割として求められているのであれば、別な路線で企画することを考えてもいいかもしれないし、やる必要がなければ、いまの共同研究というノウハウが蓄積されている範囲で、あとは本当に学術的なディシプリンにのっとった中できちんとした成果を出すところに目標を置けばいい。藤原先生が言われたように、論争を提起するということは結局ニーズを作ることになるわけですから、そういう方向でしかも学術的な価値が高いものであれば、個々の論文がさまざまな分野で引用されたりする。『20世紀システム』もいろいろ引用される部分が出てきてうれしく思っているのですが、あまり無理をせずというか、欲ばってもあまりいいことはない。われわれは本を企画するときに、最終的には必ず売り上げにはねかえってきますけれども、そこは学術書とか専門書を作る場合には禁欲的に考えてやったほうがいいのではないかと思います。
ですから必ずしも全員でやるというより、これからの方向として個別にそういうものがいくつかあって、それを出版社が出し方や宣伝の仕方を工夫して総体としてまとまったものとして読者に見えるようにする。根本的にはニーズとか何とかよりも、アカデミズムの本来のよさみたいなものを提示できればいいと思います。
『現代日本社会』はぼくが入社したときには完結していましたから、『20世紀システム』だけのことに限ってお話ししましたので、ちょっと不十分で、誤解もあるかもしれませんけれども、だいたいそんなところです。
司会 外部についてちょっと補足しますと、外部評価というのは、私の理解では、基本的にはタックスペイヤーに対してどう説明するかだと思います。それと全体研究会を外で評価するときに、6年間のプロセスは外からは見えないので、結局は出たものを評価する。もちろん売り上げの部数はごく一部で、結局は作られた本で評価されてしまう。だからさっき勝さんが言われたように、本というかたちだけが評価の対象になるのかということにすぐなると思います。ですから外部とは何なのかというときに、本として出されたものを読む読者、あるいは官僚、あるいは研究者という問題と、とりあえずこの外部評価の目的は、文部省を通じてタックスペイヤーに対してどう申し開きするかという問題と別だというのは、たしかにおっしゃるとおりだと思います。
だいぶ話が広がりましたので、いちばん最初に伊東さんの出された問題提起がありましたね。それについていままでの流れの中で伊東さんに補足をやっていただいたほうがいいと思いますので、よろしくお願いします。
伊東 一つは評価ということについて、本として表れたものは成果の一部だと思うんです。ですからいちばん基本的には、参加された、あるいは研究所の構成メンバーの先生方の研究水準がどれだけ上がったかということがいちばんの評価するべきもののはずなんです。その表面に表れてきたものが、一部本のかたちで出ているということだと思いますので、すべてについて本で評価するというのはどうか。たとえば2000万円というお金は大変大きいお金ですが、それと本というものとを比較してどうこうというのは、ちょっと短絡した話かなとは思います。
それから同じようなことですが、もしも出版社が売ろうという意識で同じ材料をいただいたとすると、たとえば6巻全部買っていただこうというのと、1冊1冊買っていただこうというのとは戦略も違ってきて、巻のタイトルについても相当意見を言うと思うんです。だから『現代日本社会』の巻のネーミングなどは典型だと思いますけれども……。(笑)褒めているつもりなんですけれども。出版社がやりますと、たとえば構造ではわからないから、もっと買いたくなるタイトルをと強くお願いすると思うんです。社研のシリーズはそういうものと違うんだと立場をはっきりされれば、そういう問題はほとんど……。
司会 たとえば有斐閣さんが出している教科書でも、最近はある意味ではものすごく工夫がされていますね。読者重視というのか。
伊東 売るためであったら、読者を自分たちで想定しイメージして、その読者が気に入るようなタイトルをつけるわけです。だけどこれは研究所がやっている仕事なんだということで、私はこれでいいと思います。逆に言うと、どの本もどの本も全部同じように読者サイドで工夫した書名をつけたり、見出しのつけ方をしたり、組み版をやったりする必要はない。そう割り切っていただきたいというのがあります。
ただ部数については、最近のものの部数は私がいくつか想像した中では最も少ない部数です。そういう意味で言うと、出版不況はこういうところにも来ているんだなという感じはしました。
廣渡 いちばん売れたのは最初の『基本的人権』で、1万5000部で、これはいまだに破られないレコードです。
伊東 そんなにたくさん売れる必要はないと思うんですけれども、これは多くはないなという感じはします。
増山 ぼくらの感覚で直感的に言いますと、『現代日本社会』はすごい、よく売れているなと思います。『20世紀システム』はまあこんなもんだなという感じです。つまりうちが出しているものの読者とかなりクロスオーバーしているので、まあそんなものだろうという感じなんです。
それと黒田さんの話に朝日の刀弥館氏の話が出て、私もずっと本の編集者をやっていますが新聞社に属しているということで若干感覚がわかるので、推測をさせてもらうと、彼は 800万読者朝日の、編集者もやっていたけれども、基本的には新聞の記者なんです。ぼくら日経は 300万読者と言われるわけです。そういう中においても朝日はレベルの高い記事が結構あるといわれるぐらいだから、彼としては自分たちを含めてもっと読者の裾野が広いと感じているのではないかと思うんです。そういう意味で一般読者のイメージは、刀弥館氏とこういう学術出版の方々とはやはり違うと思います。そういう読者が見たときに、「『20世紀システム』って何?」という話になるのではないか。だったらむしろ「20世紀」とは何だったんだろうという本のほうが、より飛び付く人が多いと言っているのではないかと思います。読者の立場からすると、20世紀を総括するという問題意識に関しては、潜在的には興味ある読者はものすごくいると思います。だけど「システム」とついてしまうと、イメージしているのとちょっと違うと思ったり、多少レベルの高い人は、ウォーラーステインの援用かと思ったり、いろいろと錯綜して、かえって社研や東大出版が想定している読者はこのぐらいのレベルのイメージかなという想定読者イメージ層みたいなのができてしまうんです。
だからぼくらだったらやり方が違うなと思ったのと、『現代日本社会』も各巻のタイトルが非常に大局的かつ抽象的ですよね。(笑)だから「すごいな。これでよく企画が通ったな」という感じがちょっとしました。(笑)
廣渡 『現代日本社会』のときに、出版会でこのタイトルで相当もめたんでしょうか。
土田 タイトルをつけるのは社研が原案は出しますが、出版会の担当者の方にもある程度相談して、両方のアイディアを入れて決まっています。
黒田 『20世紀システム』のときに限って言えば、最初に出されたいくつかのプランからはかなり話をして、変えてほしいと要望したのもありました。とくに5巻などは完全に変わりました。内容が固まる前にこちらが関与しているわけではないので、1巻の「構想と形成」とか、6巻「機能と変容」とかはある程度決まった案で動かせなかったので、こういう部分は結構悩ましいところです。
おっしゃるように一編集者として見れば、いくらでも変えたい部分がありますし、それが中身との整合性があれば、変えたほうが本当はいいんでしょうけれども、なかなかそこまで行き切らない。目次構成に関しても、作っている過程では、どうしてこのタイトルの論文がここにあるんだという疑問ももちろんあって、それは編者の方に話をしたこともあります。
結局最初に篇別構成が示されて、しかし論文として上がってきたテーマが当初の案とはまた違ったりしたときに、刊行との関係で時間の問題がありますから、最早変えられないというところはある。そこをもしうまくできれば、もうちょっと一般の人が見てこなれたものになるのではないかという感覚はあります。本を作るということに関しては一工夫、二工夫ありますけれども、そういうのは最初にある程度出版社と、話ができればたぶんいいんでしょうけれども。
あとジャーナリストの仕事というのは、これに対してこういう解答があって、それにいい意味でのレッテル貼りをうまくすることにあって、そのレッテルのよし悪しがその人の才能だと思うので、それとはここの場合は立場がはっきり違う。それがストレートにきちんと伝わってくればいちばんいいんですけどね。
馬場 アジア通貨危機とか、NATOのコソボ紛争など、これまでの通説を覆すようなことが立て続けに起こったあとでの合評会ですので、その前の時点でシリーズとして完成品を刊行しなければならなかったという点では不利なところがありますね。
司会 いま出た問題で言いますと、要するに問題発見的な企画を研究所で出していく。同時にそれを本にするということだけが大事なのではなくて、やはりプロセスを出していって、研究者を含めて刺激を相互に共有するということがあると思います。『20世紀システム』はもちろん橋本さんを中心にしてやったんですけれども、私も開発主義をやった立場から言いますと、岩波新書でタイを書いたときに、私は「開発民主主義」というタイトルを出したんですけれども、これは受け入れられなかった。あのときは全く時代にマッチしていないと言われたんです。それで開発主義の問題を必死になって考えて、この企画が出たときに最初にテーマとして出したわけです。だから弁明しますと、「開発と文化」よりはるかに早く、私は開発でまとめたいと考えた。ところが時代の流れで、いまはむしろ開発があふれんばかりで、ポスト開発などが出てきはじめた。それからアジア通貨危機になってきたら、もう一回その開発をどう取り直すかがスハルト政権が終わった後に出てきたわけです。私の中では動いていないんですけれども、そのアピールの仕方、整理の仕方というので、たぶん出版社企画の場合と、研究所の中で企画し共同研究を作っていくというのが、はっきり言ってずれてきてしまった。
いま社研が扱うような問題として、こういう流動的な状況の問題で、何が問題発見的になりうるのか。一つは、もっと基礎研究に戻ったほうがいい、歴史を含めてやったらいいのではないか、というのがある。開発主義で言うと、私は成立をきっちり押さえたら展望が開けるという立場ですけれども、アジア通貨経済危機が起こった後は、成立の問題よりも壊れた後の再建の問題のほうが一般世間では関心があります。そういう問題が出てきた。
さっきの増山さんの話が面白いと思ったのは、コアメンバーが絶えず集まって激論しながら、いまの現代日本の経済を見ていくときにどういうテーマ設定ができるかを出していく。それを社研も本来ならやるべきだと思うのですが、そのときに問題発見という中で、社研の持っているアドバンテージは何なのか。つまり個人のリーダーシップ、アイディアを中心にして動く場合と、個人では無理で研究所とかある程度共同研究が制度的に保証されているところで発信できるのと、その棲み分けもあると思うんです。もっとざっくばらんに言えば、研究所という制度で支えられた共同研究というのは、もういまの時代に合わないという考え方もありうるわけです。タックスペイヤーからすれば、もっと個人が勝負すればいいではないか。そのへんは皆さんどういうふうにお考えなんですか。
勝 どうなんでしょうね。取り扱えるテーマとかカレントな問題について研究所が何をどう発言するかという問題が一つあると思うんです。個人のレベルで言えることと、研究所としてどうだという見解を出す場合がね。たとえばコソボ紛争などはイギリスのIISSとか、所内でつねに共同研究をやっているし、中・長期的な歴史状況を見ていて、そういう中でだれかが発言する。あるいはヘッドが公式見解として発表するというかたちでさまざま介入しうるし、現実的な問題について何らかの方向性を示そうとしているということが、外部から見ていてもわかるというところがあると思います。
ただ、社研とか、あるいはほかの経済関係や社会科学系の研究所、あるいは人文科学の研究所などが、民間の研究所とはまた違ったかたちでの見解なり発言をどういうふうに出せるのか。これはかなり難しい話になってきて、そうなると現代のテーマについて何が発言できるかということを、絶えず社研の皆さん方も議論していなければならない状況が生まれてくると思うんです。
伊東 でも資料を見るとずっと全体研究というのがあるわけです。ですから絶え間なくそういう問題発見のための共同のテーブルは作っていらっしゃるわけです。出版社は、さっきのわれわれの短期的に本を作るというところから見ても、たとえば開発と民主主義というテーマがいいか悪いかという判断にしても、多くの場合、全部少しずつ遅れます。ですからそれを遅れないで、トレンドというか非常に底流のところで先に発見するという仕事は、おそらく研究所がいちばん地の利を得ているわけで、全体研究という場を確保して、できるだけ広く問題が出てきそうなテーマを、20世紀システムとか、現代日本社会とか、福祉国家とかいうテーマをずっと設定しておかれるというのは、すごくいいことだと思います。
司会 『現代日本社会』が売れているのは、1000部以上は、現代日本をどう理解してどう紹介するかというサブテキストとして高校の先生が購入したと聞いています。そこの層は結構大きかった。『現代日本社会』をキャッチするのに会社主義というテーマを立てたわけですが、高校の先生は会社主義に注目したわけではなくて、やはり「現代日本社会」で、シリーズ全巻を買って下さった。
当時日本の行くべき社会像のイメージを作るときに、社会民主主義がどうなのかとか、資本主義と社会主義の中で福祉国家という国家が介入するかたちの社会運営みたいなもので考えていた。『福祉国家』も『20世紀システム』も、現代の日本をどう見るかというのが表に出てきている。『現代日本社会』はむしろ開けてみないと何があるかわからない、一番中立的なテーマだったけれども、逆にこれで一般の読者の関心を誘った。
馬場 先ほどディシプリン・オリエンテッドか、それともテーマ・オリエンテッドかという議論が出て、黒田さんがディプリンで行くんだというのは基本的にはぼくも賛成です。ただし、ぼくの読後感からいけば、『現代日本社会』のほうは明らかに会社主義に関する論文が圧倒的に多くて、読んでいて、これは企業分析の本かなという戸惑いがやはりありました。『20世紀システム』のほうはアメリカニズムは何かということがテーマとして一貫していて、読んでみると、フォーディズムの話が3本か4本ぐらいの論文にありまして、もちろんフォードは大事だけれども、これだけ紙幅を割かなければいけないテーマなのかなと、正直いっていささか奇異な感じがしたんです。せめて各ディシプリン間で共通に踏まえられている一貫したテーマをもっと顕在化させる編集上の工夫があってもいいのではないでしょうか。
『20世紀システム』のほうは1巻と6巻が重くて、そのあいだにはさまれた2巻と5巻がだいぶ薄い印象です。何か開店したての巨大なショッピングモールの棚の商品がまだすべては陳列されていないようなイメージかな(笑)。設定されたテーマが大きすぎて、実際に詰められた中身より若干膨張してしまっているような気がします。
研究所全体が合意したテーマを長い時間かけて社研編で出すだけが、世の中にアピールする方法ではないと思います。たとえば一橋の経済研究所では、個人の研究を出すときに、一つの窓口を持って、そこで一橋経済研究所叢書というかたちにします。個々人の単著でも、全体を通すと経済研究所の一つの業績としてアピールしている。
そういうやり方で研究所のメンバーの中の特定の個人が、問題の発見をしてどんどん発表していく。社研の名前とか存在が世の中に広まるというケースと同時にそういう輻輳したシステムでやってもいいのではないかと思っているんです。
小森田 社研でも、個人の研究を似た趣旨で出しています。でもそれぞれ違った出版社から刊行されていて、それに社研の研究叢書という通し番号をつけているんです。ですから一橋の叢書に比べると目立たなくて、インパクトが少ないかもしれませんね。
増山 それぞれの版元の立場があるでしょうから、なかなか統一は出来ないでしょうが、たとえば社研の紀要なり、あるいは外にアピールするようなときに、社研の方々が書かれたものをリストにして載せたらいいんじゃないでしょうか。版元のレベルでもそういう情報が行き渡っていないのでしたら、一般の読者の方々にはもっと知られていない。それだともったいないと思います。
小森田 いまちょうどホームページで作成しているところですが、まだ出来上がっていないんです。
増山 インターネット媒体でそういう情報を発信するのはこれから先の重要な戦略ですね。
廣渡 研究叢書シリーズでいま七十何冊、それから研究報告シリーズというのがあって、これはグループ研究といってもっと小さな集団の共同研究なんですが、それを研究報告シリーズと称して56冊ぐらい出ているんですけれども、それはそれぞれの研究者が出版社と交渉して、バラバラの出版社から出ているんです。
司会 社研の全体研究のシリーズは全部社会科学研究所編です。これはタックスペイヤーに説明するときには、研究所として事業をやり、共同研究を組んでいるからこういうかたちでタイトルを出す。私もアジア経済研究所にいたときに、個人の名前で出したいと言っても、通産省は認めない。これは補助団体であって、アジア経済研究所に金を出しているんだから、その名前で出してくださいといわれる。
ところが研究所でアピールすると同時に、片方では編者の個性とかアイディアでアピールする、つまり個人の名前、あるいは連名なら橋本寿朗・藤原帰一となっていて、その下に東大社会科学研究所という名前があるということも考えられる。ここではタックスペイヤーに対するアピールと知的関心を持っている読者に対するアピールとずれてしまう。
逆に、もう一つの問題で言うと、書くほうのリスクの問題があります。個人でやるということは大胆にも書けるけれども、その責任を取らなければいけない。だけど研究所というのはそれに守られているから好きなことを書ける面もあるけれども、研究所の名前の中で書くことによって、問題発見的なものに一歩踏み込んで行かれない。両方ありますね。
馬場 その意味で言うと、社研編というかたちで出すということはブランドイメージとしての意味があると思います。それを裏づける実質的な機能として、黒田さんがおっしゃった、社研が一つのエディターシップの中心になるという発想は面白い。問題を発見して、それを有機的に外部の人脈につなげていくヘッドクォーターとしての社研の存在と機能が重要なのです。ただ今までのシリーズを見ると外部の方の参加の率が少ない気がするんです。
少し話が横道にそれますが、いまの大学改革は独立行政法人化を促されていますが、それは研究所が研究者を囲い込む危険を孕みます。それによって研究そのものがタコ壷化するという恐れをはらんでいると思うんです。
伊東 いやこの二つのシリーズでも4割か5割外部ですよ。
馬場 もっとあってもいいと思うんです。
勝 それだったら別に社研がやらなくたっていいということになる。外部の研究者の数の問題ではなくて、どのような形の機能的な役割を社研が担い、また作り上げるかということだと思う。
馬場 社研が確保すべきは問題発見の力と人を作るネットワークの力ではないでしょうか。その意味で研究所がある種サロン的機能を持つ方向が追求されてもいいのではないでしょうか。
司会 あるいはフォーラムみたいなね。
馬場 外部の研究者がある程度のメンバーシップを得るための条件をどこかで確保しながらも、相互乗り入れ自由で、ある種の問題意識が共通にあって、そこにタスクフォースができるという一種のサロンないしフォーラム的な機能ですね。インターネット駆使すれば、そういう方向に進む条件も整ってくると思います。
黒田 今回『20世紀システム』は、所外の方がわりと積極的に参加されていて、社研がそれだけネットワークを持っている、そういう機能を果たせるということの一端を示せていると思います。そのことの価値はそれだけでもものすごく高いと思います。最終的にパブリッシュするときのレベルを考えたときに、どうしてこのテーマにこの人が書いてないのかとか、一般のちょっと高いレベルの人が見たら、たぶんいろいろあると思います。そういうのをどんどん取り込んでいけるのであれば、社研にとっても非常にいいことだと思いますし、理想的なものができる。社研の、政治・法律・経済が一緒になっているという専門の幅の広さは、内部の書き手だけではたぶんアピールしきれない。
刀弥館さんが、『20世紀システム』をやるのになぜ海外の研究者が入ってないんだとおっしゃっていましたが、本当にどんどん取り込んでいって作ることも可能ですし、そうするとこういう大きなテーマだけではなくて、サブシステムみたいなテーマをいくつか積み重ねて、それに叢書という名前をつけても構いませんが、そういうかたちで年に2冊でも3冊でも刊行できるといいのではないか。
1巻などで古矢先生のああいう論文が入ってくると、性格づけも含めて後のつながりもよくなる。社研の中には、アメリカの専門家は少ないので、古矢論文がなかったらかなり厳しかったような気がしますので、それがきちんと取り込めたということは一つの成果だと思います。そういう方向で伸ばしていただければという気がします。
司会 社研は沢山の海外の日本研究者と協力関係にあって、ネットワークはあるけれども、全体研では執筆者にはいってもらったことは今まではない。出版社の企画ではどんどん外国人に入ってもらって作っていますね。最近いちばん新しく見た『鎖国を見直す』でも、巻頭の問題提起をアメリカ人に書かせている。テーマを設定するときに、そういうかたちも必要になってくるでしょう。
黒田 そういう意味では、社研は英文のジャーナルも持っていますから、そういうところで著者を開拓することもできるわけです。そういうふうに使うことももしかしたら可能かもしれません。
司会 あれはOUPから市販されている雑誌で私物化できませんので。(笑)
廣渡 さっき伊東さんが、本というのは共同研究の成果の一部であるとおっしゃったことと関連して、私たちはこういう理解をして外に示そうと思っています。プロジェクト研究というのはもちろん最終的に成果物を出して、これをもって私たちの成果ですということも重要なことなんですが、同時にプロジェクト研究に個々の所員が参加をしていく中で、自分の研究それ自体がそのプロジェクト研究の目指しているテーマや、方法的な議論や、所外の研究者との接触や、そういうことを通じて自分もそこで影響され、築かれていく。
それは個々の研究者の1人1人の基礎研究に大きな影響を与えていく。1人1人の研究者は自主的に自分のテーマを探して自分で研究しているわけですが、それを基礎にプロジェクト研究をやる。そのプロジェクト研究がフィードバックして、その1人1人の研究者の個性的な研究そのものもかたちづくっていく。その財産があるから、また次の新しいプロジェク研究が社研に固有の特性を持って展開することができる。そういう関連で理解しようではないか。
そうでないと、完全にフォーラムだということになれば、個々に所員がパーマネントに研究所にいる必要があるのかという話になってくる。プロジェクト研究を組織できるタレントを個々に確保できればいいのではないかというだけの話になるだろう。そうではなくて、そこにいる研究者が自分のフィールドを持っていて、その基礎研究をやり、同時にそれを前提にプロジェクト研究を立ち上げるという、そこにメリットを見いだすとすると、そのような相互関連性を外にアピールしなければいけない。
それからもう一つは社会的ニーズと言われているものですが、国民に分かるようなものを、という社会的要請を突き詰めていくと、"いま"起こっている問題に対して社会科学研究所はどう考えるかということを出して下さい、ということになるんです。
その論理を進めていくと、政策的な具体的な問題についてすぐ答えの出る研究所という要請になってきて、そこにも応える必要はあるんだけれども、私たちは社会科学を研究している者として、社会科学にとっていま何が重要な課題かということを見つけて、その課題について自ら解答を示す。われわれ自身が社会的ニーズが何かということを見つけて、それを提示する。それがプロジェクト研究のテーマの見つけ方の一つなんだという議論もしているんです。さっき出ていたいわばサプライサイドの問題意識でテーマを出し、本も作る。これはかなりリスキーなんですが、少なくともそういう問題意識を持ってプロジェクト研究をやってもいいのではないか。本当に社会的ニーズが何かという議論もしますが、それだけだと、いま起こっていることにただ追随して何かやらなければいけないという話だけになってしまうのではないか。それについてはどうですか。
増山 ぼくらの企画だと、コアメンバー10人ないし11人がすべてオブリゲーションを持って1冊書くというのは、いちばん最初に発行した第1巻だけです。あとはそのメンバーの中のある人間がエディターとして立って、執筆者を選んで1巻を決める。執筆者のうちの何人かがコアメンバーの中から選ばれるということはあるのですが、基本的にその時点でそのテーマについてのベストメンバーを選ぶことを目指すわけです。
それと、最初のうちはある特定の分野だけ、金融なら金融のジャンルの人たちだけを選択していたんですけれども、そのうち、たとえば都市問題を考えるときに、土木とか都市工学の人も呼んできてやる。それから法律を知らないとだめということで、法学系の人も呼んできて議論する。経済学だけではなくて、法律、政治、土木、建築、あとは官庁エコノミストとか、あるいは現場の建設会社の人なども参加して議論をするという場に、そのプロジェクトを仕上げていくというアイディアを出しました。コストの問題等で却下になったり交渉したけれども断られることもあるし、やりすぎると収拾がつかなくなるので歯止めは必要だけれども、ある程度開かれた場をという意識は研究会の上ではかなりあります。
外国人については、ある巻では、日本人4人と外国人4人がペーパーを書いて、それを比較検討したような内容のものを、外国人の書いた部分は全部翻訳をつけて日本語にして出したことがあります。
馬場 社会科学をディシプリンで切るのではなく、問題発見型にすることで、学問分野の制限が外れると思います。かつて『近代日本と植民地』というのを92年に手がけたことがあるのですが、植民地問題というのは社会科学をある意味で逸脱している。テーマ自体は問題発見型で入り口は一見狭いんですれども、そこに広がっている世界は、たとえば都市開発の問題もあるし、漁業の問題もあるし、森林資源開発の問題もあるし、鉄道建設の問題もあるし、宗教的宣撫工作の問題など宗教学からのアプローチも必要になり、必然的に学際的にせざるをえません。執筆者も、韓国、東南アジア各国、オーストラリア、アメリカも含めて、だいたい3割ぐらいは外国の方々でした。
さらにコロニアリズムは従軍慰安婦の問題など、ジェンダーの視点も問われますので、女性の執筆者も1割ぐらいいました。問題の立て方によって、執筆者も含めて柔軟にネットワークを張りめぐらせていくことが要求されてくるわけです。
勝 海外への発信ということで言えば、6巻とか7巻とかそう大きなシリーズにしないまでも、日本からの発信という意味で、日本人も英語や他の言語で書いていくような同時出版みたいな企画もあっていい。問題提起型のテーマ設定も、短期か、中期か、長期か、いろいろなテーマ設定の仕方はあると思いますが、そういうところにうまく海外の研究者とのネットワークを利用しながら、日本に対しても向けていくし、外国に対しても同時に向けられるテーマは何かということで、考える。全6巻で日本人に向けて「20世紀」ということで作るのは簡単でも、その中に外国人も半分ぐらい入れて、同時に英語でも発信したいということを考えていくと、逆に「20世紀」でいいのかどうかという問題にも実はかかわってきます。そこでまたテーマ自体の枠組みを考え直すとか、キーワードを何にするかということになる。例えば先程の話にあったように、日本の中では会社主義でも何でも通用するかもしれないけれども、それをそっくり外国人の論文を含めて同じかたちで英語でも出す、あるいは他の外国語でも構いません。そのときに、果たして書き手に同じイメージなり問題意識を共有してもらえるだろうか、また読者に理解してもらえるかどうかということを、もう少し真剣に考えていくようなことはありうるのか。
馬場 それは面白い発想だと思いますが、外国の執筆者の問題意識を汲んで、元来のエディターシップをどこまで軌道修正できるかとか、あるいはエディトリアルボード自体に外国人の発言権をどこまで入れるかという問題があって、実際上ソフト、ハード双方で相当力がいるでしょうね。
勝 でも商業出版だと、お金をかけてエディトリアルボードを作ったりということは、現実問題としてかなりしんどいわけでしょう。しかし研究所だとお金の使い方として、エディトリアルボードとして入ってもらう海外の研究者を決めて、定期的に議論をするというところに振り分けることも可能なのかなと思うんです。
司会 これはまだ実現しているわけではないのですが、開発のパラダイムというテーマで、社研とエル・コレヒオ・デ・メヒコとサセックス大学で国際共同研究プロジェクトを考えています。刊行形態は英語とスペイン語と日本語の同時出版なんです。ただし同じものを三つの言語で出すのではなくて、それぞれのニーズに応じてウエイトが変わってくる。三つの円が重なって、スペイン語でも英語でも日本語でも重なる問題提起の部分もあるし、スペイン語ではより書き込まれた実証的な研究もあるけれども、そこは英語にはしないとか、かなりフレクシブルなかたちです。全体としてはアイディアは常に交換しながら、しかも日本語と英語の2カ国語だけではなくて、スペイン語も入れる。私が入ればアジアの言語も入ってくるというかたちで、広い枠の中の共同研究として、それから出版形態もそれぞれが輪が重なりながらも、スペイン語しかない空間と英語しかないところもあるということをいま考えているんです。
増山 常に現実の社会科学的な問題に対して答えを出すようなものを社会的に要請されるのであれば、それに対して、社会科学が持っている本来のもっと幅の広さとか、あるいは国際性とか、そういったことが重要なのだと主張してもいい。それからすると、いま言われたような国際的に交流しつつ議論するものは、これまでの固定観念を打破するものとしてはすごく面白いと思います。編集作業そのものは、インターネットをつかえばたいしてコストはかからない。コストがかかるのは外国と共同のカンファレンスです。その費用をみておいて、それ以外には必要最小限のコストで処理するということで、インターナショナルなイメージを広げていく方向は、商業出版の版元ではできないことでもあるし、かなり面白さはあると思います。
馬場 日経新聞は「アジアを語る」とか「アジアの未来」などの国際交流会議を主催して、現役のビッグネームを惜しげもなく呼んできますよね。
増山 あれは新聞だからできるんです。結局出版の場合は、そこで出てきた議事録などを本にするということはできます。あれはスポンサーがいてコストが保証されているからできるし、新聞社は少々赤字をだしても体裁上やっているケースもあることはあるんです。出版局は独自にああいう企画はできないという感じです。
振り返って、普通の版元ができないようなことをやるというイメージで言えば、研究所が外国との共同研究をやるのは一つのいい方向かも知れません。
黒田 たとえば文部省から、政策的な研究とか、アクチュアルな問題に対してすぐに解答を出せという意味のことを言われるということでしたが、私は基本的には本当はそういうことはやってもしょうがないと思います。政策的なこと、いま現在の問題をやれというのは「雰囲気」みたいなもので、それは本当はアカデミズムとは全然相入れないものだと思うし、そういうことは社研としてはやらないという、いい意味の開き直りみたいなことができるかどうか質問したいのですが・・。
ジャーナリズムなどはたぶん基本的にそういう「雰囲気」でものを言うと思うのですが、そういうものに対してきちんと開き直れるかどうか。それだけの材料を持っているのかどうか。そのへんの腰の強さみたいなものを主張できるか(笑)。
ディシプリンについては、伊東さんのメモを見ても、既存の、特定のと修飾語がついているのですが、ディシプリンというのはたこ壷の縦割りみたいなかたちで、他とは相入れない独自の世界のように一般的なイメージがあるかもしれないけれども、でも本当はディシプリンがあるからインターディシプリナリーなことができるわけです。
たとえば公衆衛生を考えたときに、歴史なり何なりその分野がまずあるにしても、権力の問題とかもそこに入ってくるし、隣接した問題に必ず広がっていく。植民地の問題がさっき出ましたが、全く言われるとおりです。またそれはそれぞれ核となる部分がきちんとあってこその話です。
いまアウトプットを出して、それが即タックスペイヤーにアピールしなくてはいけないというより、学問は100年後にその成果が生きてきたって構わないわけで、そう主張して、税金をこう使っているけれども、これは将来必ず生きる、と説明したっていいのではないか。それぐらいでないと全体の「雰囲気」に対しての反論はなかなかできない。そこのふらつきが見えてしまうと、実際問題やっている研究自体がもしかしたらそうではないのかもしれないということになりかねない。
世界で何人読むんだろうという本をうちでも出しているけれども、それはなければならないわけで、すぐ役に立つ学問でなくても世界的に研究者としての評価が高い人ももちろんいますし、そういう部分は守ること自体がたぶんタックスペイヤーというか、国民にとっての財産だと思うので、それを声高に主張してもいいんじゃないでしょうか。
アメリカでも、ある種新しい発想とか、概念とか、コンセプトを出してそれを本にしたいというのが一方であって、それはそれでわかるんですけれども、でもあれは学問というわけではない。
そうすると新しい発想なり何なり、本当かどうかわからない議論を出すことがタックスペイヤーに対するアピールではないわけで、一方でさっき言った個人研究・基礎研究の大事な部分と、それも含めてそれに関連したアウトプットの部分の蓄積のすごさを日本の場合もうちょっとアピールして、むしろ対決してもらいたいなという気がします。(笑)
廣渡 いま社研の中でそういうのを整理しているんですけれども、日本の人々に対して未来をどのように選択していくかということについて、社会科学者としてきちんとした研究成果を提示する。つまり実証的、基礎的な研究を提示することが直接にその選択を左右するものとしては出てきなくても、しかしそれは大きく未来を選択する上で何らかのよすがとなるようなものをきちんとした学問的な手続きで提示したい。これが基本的な私たちの考え方なんだけれども、もっと直接的に、つまり政策志向的な研究をやる必要もあるかもしれない。そこは十分考えたほうがいいのではないだろうか。
たとえばジェンダー研究というのはもちろん基礎的な研究も必要だけれども、いまあるシステムをどのように変えるかということについて直接的な発言をしない限りは、ジェンダーの問題は一歩たりとも先へ進めない。環境問題も同じです。それから最近東大でできている情報の問題もそうですけれども、たとえばインターネットの世界についてどういうルールを作るかという問題について、「いやいや100年先に生きるものをやってますから……」ということは言えないので、基礎研究と同時に直接的にコミットする。それは社会科学者としてコミットするということは必要です。社会科学研究所が全体としてそういう課題に答えられるようなスタッフ構成と従来の蓄積があるかどうかはともかくとしても、それは課題であるということはやはり正面から受け止める必要があるだろうということまでは議論しているんです。
社研の50年のときの記念講演で、社会科学は批判科学であるというトーンで皆さんがおっしゃったわけですが、その批判が政策に結びついて、何らかの社会的なコミットができるということがなければならないのではないか。難しいところだと思いますけれども、もともとOECDの調査団が70年代の始めに日本にやってきて、日本の社会科学は政策的なコミットがあまりにも少なすぎる、これは社会科学の役割を果たしていないという批判があって以降、一般的にそのような要請が社会科学に投げかけられてきていて、社研としてはそれにちょっと距離を置く感じでいままではずっと来ていると思います。
ただ、いまのスタッフの中で議論をすれば、正面からもう少しきちんと政策的な問題を受け止めるべきだという意見はかなり強いと思います。どういうかたちでやるかが問題ですが、政府の審議会にどんどん入っていくということではなくて、学問的な問題として政策的なコミットが必要だという分野も当然ありうるし、そこはきちんと受け止めようという意見です。そうするとプロジェクト研究の中でも、先ほども出ていましたが、So What?、どうするんだ、という話も含めて、執筆をしている人たちの頭の中にその問題がないということでは困る。どこまで言えるかが問題で、これは論証を踏めばここまでしか言えない、ということはあったとしても、その問題は当然問題意識の中に含み込んで研究をするということは重要なのではないか。
司会 では所長が言われるその場合の社会科学の基礎研究というのは具体的にはどういう意味になるんですか。実証的な調査ですか。もっと哲学的なレベルまで下りた、もうちょっと時間軸の長い意味での研究ですか。そうではなくて、政策議論にも意味があるようなデータベースをきっちり作り、しかも短期ではなくて、専門家のある程度のデータ処理を経たような調査を蓄積していく、民間の委託ではなくて、それを研究所が責任を持ってやる、という方向でしょうか、またはもう少し抽象度の高い研究を片方でやりながら政策にもコミットするのか。
具体的にたとえばジェンダーという問題で、ジェンダーの基礎研究とはいったい何だろうかというのがすぐ出てきますね。ジェンダーの研究課題は何かと問うことも一つの基礎研究だろうけれども、他方ジェンダーに関する政策的なものも含めたいろいろな議論があって、その議論するためのデータベース的なものも実はない。とくにアジア諸国については、実態さえもろくに分かっていない状況で議論が出ていたりする。まず実態の調査と紹介を、ということも基礎研究に入るのか。コミットメントに対してこちらがベースとして持っている基礎研究というのは、所長のイメージとしては何なのですか。
廣渡 やっぱり記述する学問と、それからそれに基づいてこうすべきだと言う学問とあると思います。たとえばぼくはとても面白いなと思ったのは、『法の歴史の中における女性』という2400ページの本がドイツで出たんです。これは要するに、ギリシア、ローマの時代からいままでの、女性の問題を法に即して書いたものなんです。中世の法の中で女性はどういう地位にあったか、近世の自然法がどう女性について議論したか、ずっとそれを読んでいくと、なるほどなとどうしてこうなったかがわかる。
それはあくまで基礎研究です。そこから何かを言っているわけではない。そうなっているということをディスクライブしている。それをきちんとした歴史的な、実証的な手続きを踏まえて言えば、それはそれで自ずとアピールするものがあるので、社研はそういう学問をいままでやってきたんだと思いますけれども、さらにその上に立って、では何なんだということを、単なる政策的な議論としてではなくて、学問的な議論としてできるかどうかという問題を考えなければいけないのではないか。
伊東 いまの議論とずれてはいけないと思うんですが、私は社会科学というのははっきりしたディシプリンをもつものではないとしてお話をしているんです。要するに経済学とか、ある種のその方法と範囲を限定したそういうものを一応ディシプリンと考えて、それで社会科学、あるいは社会科学研究所は、さまざまなディシプリンを持った方が集まっていらっしゃる場だから、そこでやる共同研究は自ずとインターディシプリナリーになるだろう。そこで仕事をしてくださればということを申しあげているつもりなんです。
ディシプリンがはっきりしている経済学とか、法学とか、政治学というときは、たいていの場合は制度化されていて、私どもからすると市場を見つけやすい。たとえば教材としてとか、たとえば学生さんでもちょっと勉強する人とか、そうふうに想定しやすい。「社会科学」といってしまうと、おそらくそういう場面は想定しにくいと思います。それにもかかわらず現実の問題というのは社会現象として起きていることがほとんどで、そういう問題を取り上げて、つまりわれわれにとってはリスクの大きい市場の不確定なものについて、研究所で共同研究を組織されて、ある種のアウトプットをお出しになる。それを出版社として刊行できれば非常にありがたいという感じだと思います。
もう一つは、それと関係するんですけれども、おそらくこの研究所の中にいらっしゃる先生方も、一人ひとりは非常にはっきりしたディシプリンの世界におられて……。
廣渡 もともとはそうなんですけれども、ここにいるとだんだん専門の枠がにじんでくる。(笑)
伊東 よって立つところは法学の方法であるとか、経済学の方法であるとかであるけれども、その研究のスタイルも一般的に法とか経済とか言っている時代ではないので、たとえば実証を追究する方とか、非常に抽象的なところで考える方とか、それから政策志向でものを考える方とか、それから基礎研究志向というふうに、いろいろな特徴のあるスタイルでやっていらっしゃると思うんです。
そういう中で研究所がインターディシプリナリーなテーマを探したり、プロジェクトを作ったりすると、それぞれの研究スタイルでやっていらっしゃることと、社会現象をもろに提起してそこから何か探そうということとのあいだに、緊張関係が生まれるはずだと思うんです。それを共同研究の場で生かしてくださって、アウトプットを出す際には、たとえば会社主義なら会社主義というアイディアが出てきたら、それぞれの研究と会社主義というものと必ず対決させる。必ずしもシリーズの核になるアイデアに賛成でなくてもいい。そういう格好で議論の一貫した、かみ合ったものが出てくれば、本の格好になったとき、たとえば企業関係の章が非常に多くても、それは構わない。
研究のレベルのときと、コーディネーションの世界と、そしてエディターシップの世界とは少し違う。エディターシップの話のときは、われわれも意見はどんどん言いますが、研究所の共同研究の世界とそれとは少し区別したほうがいいかなと思います。
司会 コーディネーションは研究のレベルであって、エディターシップのほうはそれを成果として出す場合もあって分ける?
伊東 コーディネーションのときには、必ずしも執筆しない方でも、おそらくいろいろな方を招待して議論していらっしゃると思いますから、外へアピールするときは、さっきのプロセスの話ではありませんけれども、人を呼んで然るべきテーマで議論したものを、何らかの形でディスクロージャーすれば、それで十分ではないかという気がするんです。
司会 この研究所プロジェクトでは新しい試みとして、いま小森田さんがやっておられるんですが、ホームページで、研究会でどういう意見が出て、どういう問題提起をやっているかというプロセスをどんどん外に出し始めました。危ないなと思いながら。(笑)
小森田 私がトップバッターなんですけれどもね。
伊東 余談ですが、実は出版社はホームページは少し困るんです。本になったときには情報の中身はもう全部流出してしまっているので、商品価値が落ちる。それはちょっと要注意だなと思っているんです。
司会 ホームページを開いた人がそれに対して意見を寄せてきますね。それはこれからどうすればいいのか。
小森田 まだそのレベルまで行っていないけれども、可能性はありますね。先ほどのプロセスを大事にするというのは非常に心強いけれども、それをいまおっしゃったような問題との関係でどういうふうに表現するか。
伊東 本にするというのは限度があると思うんです。アピールのほんの一部だと思います。
司会 たとえば社研は英語でネット上のフォーラムを持っていて、あるときには 100人ぐらいがアクセスしてきて、どんどん勝手に議論を始めます。そのマネジメントだけを社研がやっているという方法を取っています。これと同じようなフォーラム方式をこういうプロジェクト型の研究でもできるんですか。これはいままでわれわれが持ってきたノウハウとは違いますね。
小森田 あまり見通しなしにやっているんですけどね。ホームページは、所外に対して社研はこういうことをしていますということを絶えず情報発信するという役割がありますが、だんだん所内の意思疎通も放っておいてはできなくなるという状況があって、所内のディスカッションの媒体という役割も重なってきている。出席していない人もいるし次につなげていくという意味もあって、所内のためにも議論の過程をホームページに出すことが重要だとは思っているんですけれども、最終的にこれが共同研究のあり方と、本のでき方にどういうインパクトを与えるのかまだわかりませんし、またそれを考えてやっているわけでもない。たしかに、注意しながらやらなければいけないとは思います。
別のことで一つだけ。いま伊東さんがおっしゃったように、社研というのは法学、政治学、経済学、最近はそれに社会学が集まって社会科学をやっている。社会現象をトータルにつかもうとしている、そこに独自の意味があるのではないかという捉え方は、社研の従来のメンバーからすれば、非常にありがたいと受け止めると思うんです。
ところがそれに対して、社会科学というだけでは社研が何をやっているかわからない、というのが外からの反応で、一つの問い掛けは政策的な役割をもっと果たせということだと思います。それと関連して、たとえばアジア経済研究所とか、あるいは人口問題とか、もっと具体的なターゲットがあるべきではないかという考え方がありうると思います。
いま社研の自己規定で、揺れながら出てきている方向の一つが、日本社会というのがなんといってもターゲットではないか。これはいろいろなコンテクストがあってそれなりの必然性があるんですが、そう自己規定もあり得るんです。
ただそれは狭い意味での日本研究者だけが集まっているという意味ではなくて、外国との比較とか、あるいは世界そのものを扱うということも当然日本社会を研究するためには必要ですから、スタッフの構成はそれによって非常に変わったり狭まったりはしないだろうとは思いますが、にもかかわらず社会科学という漠然として規定ではない、もう少し踏み込んだ規定が必要なんじゃないかというのが、いまわれわれの悩んでいるところです。
ですからおっしゃったように社会科学という普通のディシプリンの人間が一緒にやって、社会現象をトータルに追求している、そのこと自体に意味があると言って、それで存在意義を納得してもらえればいいんですが、何かプラスアルファが求められているというのがわれわれのいまの問題意識なんです。そのへんはいかがでしょうか。
司会 自己規定をもう少し明確にといって、現代日本社会を社会科学的にやりますというだけではまだターゲットが明確とはいえない……。
小森田 日本というのがはっきり入ってしまうという方向についてどう考えるかです。ずっと以前に国際問題研究所にしたらどうかとかいう議論が東大の中で持ち上がったのですが、それをはねのけて社会科学研究所でずっとやってきた。いま、名前を変えるかどうかは別として、社会科学系の日本研究機関であるという自己規定をもっとはっきりさせるという方向もあり得るんです。
増山 でも日本研究だけではない方々もたくさんいらっしゃるから、あまりそうやって自己規定することもないのではないかと思います。要するに社会科学という言葉を日本語で研究所の看板の上につけておくこと自体、古いというイメージがある人と、そうでない人といると思うんです。カタカナにしたり、新しい言葉にしたりするのがいいというのではなくて、要は実態が何をやっているかが一般の人間に伝わってくるということが、社研のまずいちばん大事なことなのではないかと思います。
そういう意味では、たとえばある事件が起こると新聞に必ずその解説記事がありますね。取材する記者が現場の記事を書いて、解説記者が問題の背景を解説する。それと同時に、電話などで取材して識者にコメントをもらう。そういうときにTVや新聞で社研の先生方が何かの問題について述べる回数は決して少なくない。だから先ほど言われた現実の問題にメンバーが答えているかというと、「答えてるじゃん」とおもうんですが。(笑)
廣渡 前に同じ日の日経の「経済教室」に河合正弘さんが出ていて、「やさしい経済学」に佐藤博樹さんが出たので、全面社研。(笑)
増山 たとえばそういうことでも社研の存在を示す。その次に経済学部と社研とどう違うのとか、政治学科と社研とどう違うのとかいう疑問が出てきたら、インターネットなり何なりでわかりやすく答える、という相互交換のシステムを新しく作っていかれれば、今来ている圧力などはねのけられるのではないかと思うんです。
小森田 いまおっしゃったことはホームページですでに一部実施しています。社研所員の発言という欄がありまして、いわゆる論文のかたちでない新聞記事とかインタビューとか、メディアに載った時事的な発言で、だれが何をしゃべったという欄を作ったんです。理想的には、そこをクリックすると中身が出てくるといいんですけれども、なかなかそれは難しい。
馬場 新聞などに書かれるものは、日々の、もっと言えば時間きざみの情報です。たとえば日本の雇用問題などは、いま失業率がアメリカを超したと騒がれますが、そのことが果たしてデートベースで問題なのか、マンスリーで問題なのか、アニュアルベースで問題なのか、それとももっと10年、20年単位の問題なのか。あるいは、アメリカと雇用問題のありようの何が違うのか、といった問題に対するアプローチのレンジが、月刊誌のレベルと日刊誌のレベルと、アカデミックな社会科学のレベルとは当然違うわけです。だけどお互いに情報や答えを融通したがっていることは確かです。
例えば日米の雇用システムの何がどう違うのかといったような構造的なロングレンジの問題にたいする疑問が、日刊誌や月刊誌のレベルからアカデミズムの研究者や機関に対してあるわけですが、常にそういった要請に対して開放系で応えられるシステムを備え、研究所としてのデータベース、基礎研究みたいなものが、そういう疑問に対して開かれていていつでもアクセスすることができるという環境と機能を持つことが、一つの存在意義を示すことになるのではないかと思います。
もう一つ、先ほど廣渡先生がディスクライブする学問と発言する学問とおっしゃいましたが、東大という最高学府の社会科学研究所は、成立したときから政策提言的な機能を宿命的に埋め込まれているのではないかと思うんです。僕ら民間の出版社やジャーナリズムは社会科学を批判科学として捉えがちですが、社研が一つの機関として歴史的に負わされてきた要請をどのように受けとめていらっしゃいますか
廣渡 1946年8月の勅令で、まだ古い体制の最後のときに生まれた研究所なんです。日本国民が明日食べるものがないという状況の中で、平和民主国家日本の建設のために、戦前型でない新しい社会科学を作る。そのために研究所が必要だと考えた。その社会科学の根本は調査、資料の収集、そして国際的な比較というのが二つの柱です。最初に経済学部の大内兵衛先生と法学部の我妻栄先生が二人で相談して作られたということです。ですからもともと新しい国家建設のために社会科学が資料を提供する、政策的にも発言するということだったと思います。それをいまの状況の中でどう受け止めて課題を設定するかという問題になります。政策との距離があんまり近まると当然問題があるわけで、そこのバランスは重要だと思います。
司会 いまたとえば私のゼミでも、学生はIMFの資料でも世銀の資料でも、即ダウンロードして、 100枚、 200枚はすぐ配ることができます。でもいまのアジアの通貨危機を見ようとおもったらIMFが流しているものをダウンロードするだけでは分からない。本当にアジア通貨危機に関して個別の国、さらに個別のコミュニティーの中で何が起こっているかを知るためには、実際インターネットでは引けない。しかし自分の目で見てと言うけれども、なかなかすぐには出来ないので、実態とか現実とか言われているものがインターネットでダウンロードされた量に還元されている。いまのアジア問題の大きな問題は、実態についての情報が意外と少ないなかで、議論だけがものすごく増えてしまったというその落差です。
どこの機関が調査をやっているかというと、民間の調査機関でも官庁でも大学でも、信頼できる調査を積み重ねていない。発言する人は増えたけれども、それを支えるためのデータや資料を提示できる人がいなくなっているという問題が起きてしまっている。これは私はいま非常に危機感を持っています。
勝 そうなってくると、スペシャリストを集めている社研みたいなところの研究者の方が、各々のテーマについて、データを蓄積してそれをどう引くか、それをどう見るかというようなこともアクセスできるようにすることが重要だと思います。それは実際かなり大変だと思います。NGOレベルまでいかないとわからない問題はたくさんある。
私たちはそれでも出版社にいて、苦労してアクセスしながらやっていく立場にいるからともかくとして、そうでない一般の人たちへの社会的還元というと、また違ったレベルで何をやりうるのかということを考えていかざるをえない。スペシャリストがいて人数なり分野もある程度分かれている研究所のようなところで、どういうかたちの基礎的なデータとか考え方を交換していくのか、あるいはアクセスできるような環境を作るのか。
伊東 成果の公開以前にデータを作る、あるいは集めるという作業について、たとえばさっき6年間で2000万という研究費の話が出てましたが、それを投入することも可能なのではないかと思うんです。昔やられたというアーバニズムの調査のような、アンケート調査でもインタビュー調査でもいいのですが、そういう調査活動をそれぞれの全体研究の中のプロジェクトとしてやったりしないんですか。たとえば『20世紀システム』とか『現代日本社会』のときにはいかがでしたか。
廣渡 もともと発足の趣旨がそういうことだったので、社研で最初に全所的にやろうとした事業が調査だったんです。農村に出かけていって農村調査をやるということで始めたんですけれども、途中で空中分解してしまったというのが出発点です。
小森田 出版物の形態として、モノグラフィーとはちょっと違った調査報告みたいなものや、データそれ自体を、非売品ですが、印刷物にするシリーズはあります。ただ、最近は出る頻度が数年に1冊という感じになってきています。
廣渡 社研がいままでやってきたのは労働調査と農村調査です。労働調査のほうは労働経済の人たちが中心になってやってきて、農村・家族調査のほうは法律学者と社会学者が中心になってやりました。だいぶデータは集まっているんです。そのデータをデータベースにして、オンラインで全世界に発信するという事業を、96年に附置された日本社会研究情報センターが、いまやっているんですけれども、さらに、新しくデータを開発するという作業を今後やらなくてはいけない。調査の部分を社研の機能としてもっと拡充していかなくてはいけないとは考えているんです。
司会 たとえばイギリスとかアメリカでトレーニングを受けて帰ってきた人は、日本には膨大な社会調査があるにもかかわらず国際比較ができるようなかたちで発表されていないし、多くのノウハウが個人の中に入ってしまっている。欧米やアジアと日本との比較を過去に遡ってやるという場合、比較できるようにするためには原表に戻って組み替える作業がいるんです。それをいまやり始めたんです。これは大変な作業で、重要な労働調査を、たとえば低所得者層の20年前の調査を、比較可能なかたちにするには10年かかるのではないかというぐらいの時間がかかります。それでないと過去の所得階層と社会移動とか社会変動をほかの国と比較することができない。
逆に国際比較ができるようなものを作ったら、今度は将来に向けて国際比較ができるルールに従ってやっていかないと、次のストックにならない。過去をもう一回見直していく作業と、未来に向けて国際比較ができる手法でデータを作っていくことと両方重ねてやっています。ただこういうのはなかなか商業ベースには乗らないと思います。
それを利用してもらうためには、今度は利用する人に対してのトレーニングとか教育も必要らしいんです。
勝 おそらく比較をするためには何らかのルールというか、国際基準にのっとったやり方があって、そういう基礎データをいま作り始めている状態だとすると、できたからといって同じように議論できるかといえば、おそらくできない。使いこなせないという状況が、いまの研究者としてはあるんだと思うんです。
司会 そろそろ時間が押してきましたので、ぜひということがあれば出してください。
馬場 全体研究にはたぶんならないと思いますが、サブ的なテーマでぜひやってほしいと思っているのは、日本の社会科学の起源と展開と変容という問題というか、日本近代の社会科学者の延長線上にある研究者の一種の責任をぜひ掘り起こしてほしいという気がします。
社研が発足した経緯を見ても、それまでの植民地政策学や植民地経済学の流れがどこかに伏流としてあったはずです。和田春樹先生のエッセイで読んだのですが、当初矢内原所長をはじめとして5人の研究スタッフのうちの4人が、旧植民地の台湾や朝鮮の研究機関や大学から招聘されて、植民地経済学を国際経済学と名を変えて講座を設けたということでした。別に植民地主義を批判したり謝罪させたりすることが目的なのではなく、なぜ今日このような社会科学が日本に育ったのかという素性というか成り立ちを知りたい。別に社会科学だけではなくて、文学だって、文化人類学だっていろいろな経緯があったと思いますが、みんな封印されたままです。ディシプリンの内容や方法が中心ですけれども、研究機関の変遷とか、人脈の経緯とか、あるいは人事のあり方とかいったことも含めて、検討していただければと思います。そういうことだったら編集者としてぜひ乗りたいなと思いますし(笑)。
廣渡 戦後の日本の社会科学というテーマで特定研究費を取って、社研で3、4年やったことがあります。結局成果物にはなりませんでしたけれども。それからいつも全体研究のテーマに困ると、社会科学論をやったらどうだ、となる(笑)。これは究極のテーマなんです。
伊東 ところでこの『20世紀システム』の後のプロジェクトはもう始まっているのですか。
廣渡 いや、いま議論中です。ちょっとさわりをひと言だけ紹介したらどうですか。まださわりもできていないんだけれども。
司会 一つは、やはり『20世紀システム』はオイルショックを乗り切ったところまでは書いているけれども、90年代の長期不況は書いていない、アジアも通貨経済危機までは入ってない、アメリカは好景気になってしまったという状況の中で、『20世紀システム』の後を正面に据えたものを取り上げてほしいという要請はあると思う。ただしその続編としてやるわけではありません。どういう角度で見るかで、いま五つから六つの複数のプロジェクト案を出していて、それを相互に重ね合わせながらやっていく方法を考えています。先ほど紹介した中川さんのメキシコと、サセックスと、社研と、それから河合さんが世銀に出向していますので世銀と共同で開発のパラダイムを考えるというのが一つです。
それから小森田さんや私で考えているのは、東欧・ロシアとラテンアメリカとアジアを対象にして、自由化と経済危機の流れを、相互乗り入れしながら大胆に比較するということも考えている。複数のプロジェクトの核になるプロジェクトでは、今回の長期構造的不況を日本の経済、政治、社会のシステムとからめてもう一回総合的に捉え直す。そこに私たちのさっき言った東欧とかアジアとかラテンアメリカの研究も参加して比較していくとか、いろいろ相互浸透する。それから国際機関を含めて開発をやっている人たちにも入ってもらう。あるいは食料問題をやっている人たちも参加して比較する。
いままでのように大鑑巨砲主義ではなくて、あるコアを作りながら、その周りに三つか四つあって、それが自由に出入りしながらお互いに刺激を与えて研究していく。成果物としてはコアを中心にして社研をアピールするけれども、研究のプロセスとしてはもうちょっとフレクシブルになります。分科会方式ではなくて、インディペンデントになりながら、連邦型と言うんですか?……。
廣渡 できたらそれに21世紀をどう展望できるかというメッセージが入るといいなと思っています。
司会 あとどうですか。増山さんいいですか。
増山 ぼくらみたいに社研の方々とかかわりがある人間だと、社研というのは何なのかというのはわりとわかっているつもりです。にもかかわらず今日話されたような問題が出てきているということは、やはり情報がそれほどうまく発信されていないのではないか。そこの部分がもうちょっとクリアに出されれば、そんなに問題はないのではないか。この大きなプロジェクトだけが社研のレーゾンデートルだというのではなくて、先程の社会科学研究所叢書もあるわけですから、それがもっと外の人間によく見えるようにする。たとえば一括して一つの出版社に任せるとか。新しい社会科学研究所研究叢書と一新して、たとえば東大出版会から1巻、2巻、3巻と継続して出すなど。全体研成果のようなものも何年かに一度バーンと刊行されるし、叢書もどんどん出ているということになって、マーケットにも読者にも結構知れ渡る。さらにインターネットで情報を流すということもあると、全体として社研の存在をアピールして、しかもだれがどんなことをやっているかという活動の内容もより明らかになるのではないか。それだけきょうはずっと考えながら来ましたので、そんなところで。
黒田 先程の「日本社会」をターゲットにという話について。そういう旗のふり上げ方ばかりでなく、さっきのデータの集積とか個別の調査とかいろいろ基礎的な研究とかがたぶん社研にとっては核になる部分だと思うので、「日本社会」を旗として掲げてもまだ茫漠としていて、単にまとめるときにいい言葉がないからタイトルにつけるみたいな感じになってしまうので、そういうのは得策ではない。もっとやれることがあるし、実際やっていることがあるわけですから、それをうまく利用したほうがいいのではないかという気がします。なるべくそのお手伝いができればとは思います。
廣渡 きょうは長時間にわたりまして大変ありがとうございました。社研のスタッフもこれほどまでには社研のいろいろなことに立ち入ってまだ議論したことがないという感じがいたします。どうも本当にありがとうございました。痒いところに手が届くようなご指摘をたくさん受けまして、ずいぶん参考になりました。これは私たちのほうでまとめまして、最初に申しましたように、専門家パネルの検討の結果として外部評価委員のほうに提出させていただこうと思っております。その過程でまた、こういうことでよろしいかどうか、きょうのご討議をまとめたものについてお伺いすることもあるかと思いますので、もう少しご協力のほどをお願いいたします。
それから、今日とてもよかったので、また時々こういうご意見を伺う会を……。(笑)実は外部評価というのは1回限りでやるものではないということを強調しておりまして、大学自体も恒常的に外部の人間を入れた運営諮問会議を作るということが法律改正で決まっていますけれども、それぞれの部局でも、きちんと第三者の意見を聞きながら、まさに国民へのアカウンタビリティーを高めるために、これは掛け値なしにそのとおり重要だと思っていますので、今後ともいろいろお世話になるかと思います。よろしくお願いしたいと思います。きょうはどうも長時間ありがとうございました。