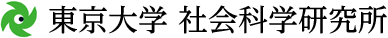案内
- トップ
- 外部評価報告書
- 付属文書1. 全所的プロジェクト研究についての専門家パネル
- 2. 専門家パネルの開催の趣旨並びに出席者の発言要旨
外部評価報告書
<提出資料> 付属文書1. 全所的プロジェクト研究についての専門家パネル
2. 専門家パネルの開催の趣旨並びに出席者の発言要旨
(1)専門家パネル開催の趣旨
東京大学社会科学研究所では、1969年から都合6回にわたって全体研究会(全所的プロジェクト研究)を組織してきた。ここ10年間では、『現代日本社会』(全7巻、東京大学出版会)と『20世紀システム』(全6巻、同上)の刊行がある。全所的プロジェクト研究は、共同研究のテーマ設定からはじまって、研究会の組織化とその運営、成果の出版計画と刊行にいたるまで、研究所のスタッフが直接関与し、責任をもって運営する仕組みに大きな特徴がある。しかし、共同研究の準備段階から成果の刊行に至るまでは、平均して5ー6年間の期間がかかっており、同時にプロジェクトに投入する労力とコストも決して少なくない。
一方、シリーズものの刊行や共同研究の成果の出版については、出版社主導のものや学会主導のもの、あるいは研究者が随時集まってアドホックな編集企画委員会を組織し、必要に応じて本を作成するものなど、さまざまな形態がある。したがって、今回の専門家パネルでは、社会科学研究所のように国立大学の附置研究所が、共同研究の企画から出版まで運営することの意義と問題点について、外部者から率直な意見を得ることを第一義の目的とした。
ところで、全所的プロジェクトの成果の学術的評価については、研究所は過去、各シリーズ各巻ごとに関連する専門家や研究者に検討を依頼し、検討者を招聘して合評会を開催し、その結果を研究所の紀要である『社会科学研究』に逐次掲載してきた。そこでこの専門家パネルでは、社会科学系の代表的な出版社の編集者に参集していただき、あくまで出版社・編集者の立場から、社会科学研究所の全所的プロジェクト研究について、その企画の内容や成果の社会的還元の方法も含めて、自由で忌憚のない意見を披瀝してもらうことにした。
専門家パネルは99年6月19日に研究所の所長応接室で実施した。討議は具体的な提言や批判も交えて約3時間、当初予定していた休憩を返上してきわめて熱心に続けられた。そのパネル討議の詳しい内容は別紙のとおりであるが、ここではその発言の要旨のみを摘記する。
(2) 出席者
◆編集・出版関係者(外部評価者) 計5名
*伊東 晋氏 有斐閣編集部
*増山 修氏 日本経済新聞社出版局
*馬場公彦氏 岩波書店『世界』編集部
*勝 康裕氏 同文舘出版営業部
*黒田拓也氏 東京大学出版会編集部
◆社会科学研究所側出席者 計6名
*廣渡清吾社会科学研究所所長
*小森田秋夫外部評価実施委員
*末廣昭外部評価実施委員・全所的プロジェクト専門家パネル担当(司会)
*土田とも子(全所的プロジェクト担当者)
*箕輪太郎(業務掛長)
*速記者・テープ管理者
(3) 専門家パネルでの発言要旨
伊東氏/論点を整理したレジュメ2枚を配付。
- 出版社サイドでは、「全体研究会」のような長期的な共同研究を企画し、編集を準備する体制も人件費(編集者の機会費用)も望めない。読者の関心やメディアの選択の変わる速度が大きく、短期的対応に迫られているのが実情である。本来、出版社と研究所の間には「棲み分け」があり、研究所はそれに応えていると判断する。
- シリーズものを企画することは、出版社サイドでももちろん可能であるが、どうしても既存のディシプリンや特定の切り口に依存した既存個別研究の集積にならざるをえない。単なる編集作業を超えて、共同のフィールドワークまでも含むような共同研究作業は、通常の出版社では到底無理であり、そこに研究所による共同研究の存在意義もあるし、期待したい。
- 分析対象の探索・設定から研究成果の収穫までをインターディシプリナリーなプロジェクトを作って遂行することは研究機関の重要な役割であり、その成果を出版するかどうかは二義的にすぎないとも考えうる。また、出版に際して需要側の嗜好や関心に従ってタイトルや記述方法を考えるのではなく、研究そのものの内容を無駄なく示すことこそが、研究所にとってはより重要であろう。
増山氏
- 現在、日本経済新聞社出版局では、編集部と大学教授・官庁エコノミストのコアメンバーで構成する「現代経済研究会」を設置し、内部に事務局をおいて、年2冊の頻度でシリーズ本を刊行している。2カ月に1回のペースで手弁当の研究会を開催し、今後出版すべき本の内容や執筆者陣の検討を行い、一定程度構想が固まると、ミニ・コンファランスを開催している。企画は大体半年から1年間をめどに実施し、刊行がその期間を超えると「out of date」になる。
- 数年後に予定されている動向(EU通貨統合など)に照準をあて、あらかじめ編集企画を考えることも、我々としては重要視している。ただし、中期的出版計画について言えば、テーマが変わったり、予定執筆者が海外にでたりといったリスクがあり、同時に営業担当もシリーズが長期化することには、販売促進の面から消極的である。そのあたりが、研究所の企画とは異なるとは異なる思う。
馬場氏
- 岩波書店の出版物は、定説化している議論からなる「講座もの」、学会のヒエラルキーなどに縛られないで企画する「シリーズ」「叢書」、個人の研究成果の単行本の3つから構成されている。定説や通説を啓蒙的に紹介する企画が必要であるにもかかわらず、従来の学会のヒエラルキーに即して企画すると一般読者や他分野の研究者に対するインパクトが弱くなってしまうというジレンマが生じる。そうなると、どうしても「問題先行型」の企画が要請されることになる。
- 研究所の過去の刊行物をみる限り、テーマの広がりや中立性において、とくに違和感は感じない。ただし、大切なことは「現代を読み解く」ためのパラダイムの提示であり、研究所はその意味で「問題発見型」の研究企画をもっと鮮明に打ち出す必要があるのではないのか。
- 社会科学は本来、政策科学であり批判科学である。「社会的ニーズ」という場合、誰が対象なのか。本を購入する一般読者なのか、論壇なのか、専門の研究者なのか、それとも官庁や政治家など政策関係者なのか。今の研究企画では一般読者にしろ政策関係者にしろ、どちらからもまだ距離があるように思う。社研という公的研究機関のポジションから考えて、批判的政策科学の性格を強く押しだし、もっと政策関係者を対象にしてもよいのではないのかというのが、私の意見だ。
- 『20世紀システム』では、序論、あとがき、索引などに工夫がなされている。ただし、読者がもっとヴァーチャルな意味での編集過程に参加できる工夫も必要であろう。その意味で、各論文が作品化されていくプロセスを『月報』の形で紹介する方法もある。
勝氏
- 現在のように商業出版が厳しい状況に置かれているもとでは、よい企画をたてることと、それが出版できるかどうかはまったく別の問題と考えるべきである。現実には多くの出版社では人員不足に悩んでいる面もあり、編集者の質の低下も問題になっている。かりにすぐれたシリーズの企画があっても、それを実現することはきわめて難しい。その点、研究所は有利な立場にある。
- 研究所にとって、研究成果を本に仕上げ刊行することだけが、果たして最終目標だろうか。今日のように社会科学が時代状況に振り回されているときには、共同研究の成果だけでなく、成果にいたる議論のプロセスそのものを活字化していくことにも意義があると思う。また、公開するかどうかは別にして、一度書いた草稿を執筆者が他の草稿を見ながらあらためて手を入れていく作業自体も、研究所のような共同研究では可能かつ必要なプロセスである。
黒田氏
- 社会科学研究所の出版とは別に、別の研究会(4ー5年の期間)の成果を学術書として刊行していく仕事にも従事している。その経験からいうと、先ほどから言われている、研究のプロセスを活字にしていく必要性には疑問が残る。
- 共同研究について言えば、一般読者におもねる必要はない。もっと研究の対象である事実関係を明確にし、論点を整理することに力点を置くべきであろう。『20世紀システム』の場合、それに該当する論文がいくつもある。
- 『20世紀システム』の第6巻の合評会の記録には、新聞社に勤める検討者が、「執筆者はもっと外部(世間)のニーズを意識すべきである」とか、「各論文にそれぞれのテーマの記述はあるが、だからどうなのだという、 for what の論議が欠けている」という批判があった。もっともな議論ではあるが、私はそれとはやや違う考えを持っている。研究所が刊行するものとしては、もっとアカデミズムの社会を読者として想定すべきであるし、『20世紀システム』の編者のひとりである藤原氏が強調したように、「読者の間に論争をつくりだす」ことこそが重要であろう。研究所としては、アカデミズムのニーズをつくりだすような「本作り」を考えるべきである。
伊東氏
- 出版物としての本は研究成果の一部であって、研究者の水準が共同研究を通じて向上するかどうかが、本来は問題とされるべきである。このことができるのは研究所であろう。出版社の場合には、かりに同じ企画ものがあったとしても、それをシリーズで刊行するか、それとも単著として別々に刊行するかは、読者の好みと出版・編集側の要請で決まるし、出版に際しては割り切っている。研究所の出版物はそうではないところに意義がある。
増山氏
- 『現代日本社会』も『20世紀システム』も、各巻3000部から7000部という販売実績をあげており、率直に言って研究書の売り上げとしては「よく売れている」という印象をもつ。一方、新聞社の世界では、書くものについては「800万読者」とか「300万読者」が絶えず念頭にあり、読者のニーズの裾野はきわめて広い。そのため、読者のデマンドを絞りこむこともきわめて難しい。その点、研究所はもっと読者層を明確に規定できるし、そうすべきであろう。
黒田氏
- 政策志向的研究について言えば、基礎研究や今の政策・制度を批判的に検討することも不可欠な仕事である。インターディシプリンな研究が可能になるのは、既存の特定のディシプリンについてしっかりした研究があるからこその側面もある。その意味で、研究所がいたずらにふらつく必要はないし、もっと自信をもつべきである。社会科学の基本を守ることこそが学術研究にとって財産になることはあるし、単なる思いつきだけでは社会科学は続かない。研究所の意義はそういうところにある。
馬場氏
- その意味では、研究所には「日本における社会科学研究の素性」、つまり「日本における社会科学の起源・展開・変容」といったテーマをもっと取り上げて掘り下げてほしい。例えば、社会科学研究所が「50周年記念」事業として取り上げたような、日本のアジア関係の研究所の成り立ちや、過去の植民地政策学の系譜・人脈などは、大変関心があるし、社研のような研究機関がそういった問題を取り上げることは一つの責務ともいえるのではないか。
伊東氏
- 個別科学としてディシプリンがすでに制度化されている分野では、読者層という「市場」を見い出すことは比較的やさしいといえる。ところが現実に日々起こる社会現象はそうした制度化されたディシプリンの枠の外で生じているわけで、したがって、予めシリーズという形での本の市場を見い出すことも難しい。このリスクを社会科学研究所のような研究所が引き受けることにこそ、研究所の本来の意義があると思う。当然、日々起きている社会現象と個々の研究者が作ってきた研究スタイルの間には緊張も生じるが、この両者があえて「対決」することで、研究所の共同研究がもつ積極的な意義、つまり「coordination」の強みを発揮してほしいと思う。
以上の議論のほか、討論者から次のような意見・提言も寄せられた。
- 東京大学社会科学研究所の「ブランド」を前面に出した「研究叢書」を刊行し、刊行物に研究所の名前を賦して対外的にアッピールすべきではないか(馬場氏、増山氏)。
- 共同研究にあたって、外国人研究者をもっと執筆者にとりこむべきではないのか(馬場氏、勝氏)。
- 共同研究の成果を日本語だけでなく、英語など他の言語でも出版すべきではないのか。さらに研究の国際的ネットワーク化も必要ではないのか(勝氏)。
- 共同研究の成果還元を出版物だけではなく、研究者の人的ネットワークや「研究サロン」の形で発展させるべきではないのか(馬場氏)。研究会の形式にこだわるのではなく、もっと双方性の情報交流を進めるべきではないのか(増山氏)。
- 社会科学の基礎をなす基本データの整備にもっと力をいれてほしい。
- ①については、あまり知られていないようだが、すでに「東京大学社会科学研究所研究叢書」の名前で合計77冊の刊行実績があること。ただし多数の出版社にまたがっているため、社会的インパクトが薄いかもしれないとの回答を行った。
- ②と③については、すでにスタッフの中川氏を中心とする「開発パラダイム国際比較研究会」が、社会科学研究所、メキシコのコレヒオ・メヒコ大学、イギリスのサセックス大学、世界銀行の4機関をコアに、同一テーマについて日本語、英語、スペイン語の論文の同時出版や研究交流を企画している旨を回答した。
- ④については、研究所スタッフの原則的参加を前提とする従来の「全体研究」方式を脱却して、「研究フォーラム」形式などを重視した柔軟かつ多層的な研究会の組織化とその連合による「全所的プロジェクト研究」方式に、現在移行しつつあると回答した。
- ⑤については、日本社会研究情報センターの「データ・アーカイブ」班で、すでに過去の労働調査のデータの加工処理や朝日新聞との連携で情報処理を行っていること、問題はデータの再構築だけではなく、そのデータを読み解き分析できるだけの若手研究者を同時に養成する教育過程にこそあることを強調した。
これらの回答については、いずれの討論者からも高い関心をもって歓迎されたことを付記する。