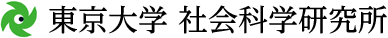案内
新刊著者訪問 第46回
企業法学の方法
著者:田中 亘
東京大学出版会 2024年:5,800円(税抜)
このページでは、社研の研究活動の紹介を目的として、社研所員の最近の著作についてインタビューを行っています。
第46回は、田中 亘『企業法学の方法』(東京大学出版会、2024年) をご紹介します。
――はじめに、この本の内容を簡単に教えてください。
本書は、私がこれまで公表してきた研究論文のうち、「企業法学の方法」というテーマに関連したものを選んで纏めた論文集です。本書には、私の専門である企業法の領域において、解釈論や立法論をどのような方法で行うことが望ましいのかを論じた論文(本書第1部所収)と、そのような方法論的な問題を意識しながら、企業法の具体的な諸問題について論じた論文(本書第2部所収)とを収録しています。
なお、「企業」とは、営利目的で組織的、継続的に事業活動をする経済主体のことであり、「企業法」(「商法」ともいいます)とは、企業の組織や活動について規律する法制度のことをいいます。株式会社を初めとする会社についての法律である「会社法」(平成17年法86号)が典型です。私は、これまで会社法を中心に研究してきましたので、第2部所収の論文の半分は会社法に関するものですが、残り半分は、担保法や倒産法など、会社法以外の企業法の問題について論じています。
また、本書の冒頭には、「序論」と題して、私が企業法学の方法に関してどのような問題意識のもとに研究を行い、その結果、現在どのような考えを持つに至ったか、また、何を将来の課題と考えているのかを説明した書き下ろし論文を収録しています。「効率性」とか「社会厚生」など、本書で頻出する経済学の概念についても説明していますので、本書の読者は、まず「序論」に目を通していただければと思います。
――解釈論や立法論の「方法」というと、ずいぶん難しそうなテーマですが、どのようにして研究を進めているのでしょうか。
日本において、法解釈の方法論として有力に主張されてきたものに、「利益衡量論」(または「利益考量論」。以下、両者を併せて「利益衡(考)量論」といいます)があります。利益衡(考)両論は、昭和40年代頃に、民法学者である加藤一郎や星野栄一が提唱したもので、その中心的な主張は、(1) 法解釈の決め手となるのは、どのような価値をどのように実現し、どのような利益をどのように保護すべきかという判断、すなわち価値判断であること、および、(2) そのような価値判断をするに際しては、問題になっている法令の規定について可能ないくつかの解釈をとると、どのような人のどのような利益が、どのように実現・保護され、あるいは実現・保護されないのかを徹底的につきつめること、つまり利益衡(考)量が必要である、とする点にあります。なお、利益衡(考)量論は、もともとは解釈論の方法として提唱されたものですが、提唱者の一人である星野は、その方法論は立法論にも用いることができると明言しています。
私は、法学部生時代に利益衡(考)量論に教わったときから、この主張に強く賛同し、法学者として立法論や解釈論をする際にも、利益衡(考)量論によっていました。ただ、同時に、利益衡(考)量論に対しては疑問というか、不満も感じていました。
――「不満」とは、具体的にはどういうことでしょうか。
二つあります。一つは、既存の法の解釈であれ立法であれ、何らかの法制度の設計(本書では、法解釈と立法をまとめて「法制度の設計」と呼んでいますので、以下でもそのようにいいます)をするときに、どのような人のどのような利益が実現・保護され、あるいは実現・保護されないのかを「徹底的につきつめる」ための分析ツールを、法学は十分に持っていないように思われたことです。法制度が人々の利益にどういう影響を与えるのかを分析するためには、法制度の直接的な効果、つまり、その法制度が人々にどういう権利を与え、または義務や責任を課すかを見るだけでは十分ではありません。法制度の間接的な効果、つまり、その法制度の下で人々がどのように行動し、その結果として、人々にどういう利益や不利益をもたらすのかについても考える必要があります。
ところが、伝統的な法学は、法制度が人々の行動、ひいては人々の利益にどういう影響を及ぼすのかを分析するための体系的な方法を必ずしも発展させてきませんでした。そのため、法学の議論では、法制度の間接的な効果については考慮されていなかったり、あるいは考慮されていたとしても、個々の論者の、多分に経験や直観に依存した考察に委ねられていることが多いように思います。また、法制度が期待されたような利益を人々にもたらしたのかを事後的に検証するためのツールも、伝統的な法学は十分に発展させてこなかったように思われます。
私のこのような問題意識は、立法論や解釈論を行うに際し、関係諸科学を積極的に活用するべきであるとの提言、および、自身の研究活動におけるその実践につながりました。特に、1960年代頃から主に米国で発展してきた、法制度を経済学の手法を用いて分析する「法と経済学」(または「法の経済分析」)という学問分野は、法制度が人々の利益に与える効果の予測および事後的な検証のための有用なツールを発展させています。そこで、法と経済学について勉強し、自身の研究に活用してきました。本書所収の論文は、いずれも、そうした法と経済学の研究成果を取り入れたものになっています。
――利益衡(考)量論に対する「不満」は二つあるとおっしゃいました。もう一つの不満について教えてください。
利益衡(考)量論が、解釈論や立法論の「決め手」であるとする価値判断をどのようにして行うのかを明らかにしてこなかったことが、もう一つの不満です。法解釈であれ立法であれ、およそ何らかの法制度の設計をすると、それによって利益を得る人と不利益を被る人が出てくることが通常です。どんな利益や不利益が生じるのかを「徹底的につきつめる」ことはいいとして、つきつめた後に、それでは誰のどういう利益を優先して法制度の設計をすることが望ましいのか。そういう望ましさの判断をどういう方法で行うのか。利益衡(考)量論の提唱者は、そこは「常識」で判断するのだ、といったことを述べているのですが、常識がいつも正しいとはいえないように思いますし、そもそも何が常識なのかについて人々の意見が一致しないこともままあると思えまして、そこが大きな不満でした。
――その不満は、本書では解決しているのでしょうか。価値判断を行う方法について、本書はどんな結論をとっているのでしょうか。
これは、非常に難しい問題で、実をいえば本書でも、確定的な結論は得られていません。ただ、本書全体を通じて強く打ち出している立場は、「法制度がもたらす利益の大きさを比較することが大事だ」というものです。何らかの社会問題を解決する際に、とりうる法制度の選択肢が二つあり、どちらをとることが望ましいかを判断しようとする場合を考えましょう。その際は、「どちらの法制度のほうが、社会の人々に対し、全体としてより多くの利益をもたらすか?」ということが、法制度の望ましさの判断にとって、唯一の考慮要素とまではいえないとしても、非常に重要な考慮要素になるというのが、本書の主張です。
――「全体としてより多くの利益を人々にもたらす」法制度が何かを判断できるのですか。法制度によって利益を得る人もいれば、不利益を被る人もいるはずですが、それらの利益・不利益は全部合算するということでしょうか。
はい。利益も不利益(マイナスの利益)も、誰に生じるかを問わず合算して、ネットの利益が大きくなるような法制度が望ましい、少なくとも、望ましさの判断のための重要な考慮要素になる、という立場です。
――異なる人の利益とか不利益を合算できるものでしょうか。そもそも、利益の大きさをどのように測るのでしょうか。
それは、法と経済学において、あるいは道徳哲学や厚生経済学において古くから論じられてきた問題です。例えば、功利主義という思想は、異なる人々の効用(utility)――この言葉が正確に何を意味するのかは議論があり、本書でも説明していますが、さしあたり、「満足」とか「幸福」のような意味だと理解してください――であってもそれらを比較したり、合算したりすることができるという考えのもとに、効用の総和が大きくなることが望ましいとする考え方です。
私も、異なる人の効用であっても比較も合算も可能だと考えています。そして、それを前提に、ある人に生じる利益の大きさは、その利益がその人にもたらす効用の大きさで測ることが、本来は適切であると考えます。
ただし、従来、法と経済学では、異なる人の効用の大きさを比較することはそもそも不可能であるとか、あるいは原理的に可能であるとしても実際上比較は難しいという考えから、ある人に生じる利益の大きさは、その人がその利益に対してつける金銭評価額(その利益を手に入れるために、いくらの金銭までなら支払う用意があるか)によって測るという立場が有力です。そして、そのように金銭評価額で測った利益が最も大きくなる法制度が望ましいと考えます。これは、「効率性(efficiency)」という基準です。効率性基準は、本書「序論」で論じているように、かなり重大な欠点があります。しかし、私は、こと自分の専門分野である企業法の諸問題について考える上では、欠点に留意しながらも効率性基準を用いて法制度の望ましさを判断することが、基本的に適切だと考えています。
――効率性だけで法制度の望ましさを判断できるとは思えないのですが。社会正義とか、公正とかの観点も重要ではないですか。
そのように考える人が多いだろうと思います。ただ、効率性基準を使って四半世紀くらい企業法を研究してきた者の実感として、次の2点はいわせてください。
一つは、一般には公正とか正義の観点から支持されているであろう法制度ないし法規範は、その制度なり規範が社会に普及し、多くの人々がそれに従って行動すると、社会の人々に生じるネットの利益が増大すると期待できるので、効率性の観点からも支持できることが多いのです。例えば、大抵の人は、詐欺は不公正で不正義だと考えるでしょうが、詐欺が認められているような社会では、人々は他人が提供する情報は信じられなくなるので、いちいち情報の真偽を確認しないと取引できなくなるでしょう。それでは、本当はお互いの利益となるような取引が成立しなくなるなど、非効率な事態が生じてしまいます。従って、法制度が詐欺を禁じることは、効率性の観点からも支持できます。
第2の点ですが、正義や公正の観点からは、どういう法解釈なり立法を支持すべきなのかがわからない、つまり、公正観念が法律問題の解決のための指針を与えてくれない、と思われる場合が、実際には多いのです。本書で取り上げている法律問題を例にしますと、敵対的買収に対して取締役会が防衛策を行使することがどこまで認められるかとか、倒産手続において担保権の効力をどこまで制限するべきか、といったことについて、公正の観点から何が言えるのか、はっきりしません。そうした問題についても、効率性を基準にして、経済学の知見を踏まえて考えると、どのような場合にどのような法制度が望ましいかについて、有益な洞察が得られると思われる場合が多かったのです。
私のこのような認識が適切かどうかは、本書に収録した論文によって、読者に判断してもらうほかありません。ともあれ、私としては、一人でも多くの読者が、本書で用いているような分析手法が、少なくも企業法の分野では、法制度の望ましさを判断するための有力な分析手法であると認めてくれることを願っています。
――どうもありがとうございました。
(2025年1月10日掲載)