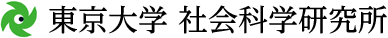案内
新刊著者訪問 第28回
『フランス法における返還請求の諸法理 原状回復と不当利得』
著者:齋藤哲志
有斐閣 2016年:9000円(税抜)
このページでは、社研の研究活動の紹介を目的として、社研所員の最近の著作についてインタビューを行っています。
第28回は、齋藤哲志『フランス法における返還請求の諸法理 原状回復と不当利得』(有斐閣2016年8月)をご紹介します。
- 目次詳細はこちらへ
- 主要業績
- Droit du Japon, Bibliothèque de l'Association Henri Capitant, L.G.D.J., juillet 2016, 106 p
- 「フランス都市法におけるソーシャル・ミックスと所有権」吉田克己・角松生史編『都市空間のガバナンスと法』信山社、2016年
- 「用益権の法的性質—終身性と分肢権性」日仏法学28号、2015年


――フランスは今年5月に新大統領が就任していろいろ話題が多いですね。先生からご覧になってフランスってどういう国ですか?
フランスとの付き合いはそれなりに長くなってきましたが、まだまだ謎だらけです。挙げていただいた選挙に関していえば、大統領選はよいとして、その後の国民議会選挙で大統領与党があれだけ勝ってしまうとは。フランスという国はときにこちらの想定を裏切ってくるので飽きずにいられます。

今年3月のソルボンヌ
――先生のご専門は「フランス法」とのこと、丸ごと全部というのはちょっと面食らってしまうのですが、本書のテーマである「返還請求」というのは、フランス法の中でも民法ですよね?
そうですよね、明らかに羊頭狗肉です…。本書の冒頭でも書いたとおり、実質的にこの研究は民法に括られるものです。民法であれ他の実定法分野であれ、日本の法学研究者は外国法研究からキャリアをスタートさせるのが通例になっていますので、私もあえて「フランス法」を掲げる必然性は乏しいでしょう。それでも意義を標榜するとすれば、フランスで生起する法現象を深くかつトータルに認識できるように努めている、ということになるでしょうか。ある種の地域研究のようなもので、あらかじめ帰ってくる場所として自国法を前提とせずに、彼の地で紡がれてきた法的な諸言説を眺めてみるという感じです。とはいえ、問い自体は日本法(及びドイツ法)から立てていますから、フランスの研究者が自国法を検討するというのとは性質が異なるわけで、自分の帰属先はどこなのか、そもそもそんなものはあるのか、と日々頭を悩ませています。
本書ではそうした迷いを一旦封印して、フランスの学説・判例・立法にべったり張り付いてみる、という方針で臨みました。フランス法は日本の近代以降の法に陰に日向に大きな影響を与えましたから、同じ枠組みで物事を論じているであろうとの予測が立ちそうです。しかし少し遡るだけで、予測は見事に裏切られます。例えば非常に基本的なカテゴリーである契約の「無効」と「取消し」も、同一にみえる用語は存在しますが、歴史的に生じたローマ法とフランス法との対抗的な関係の下、区別の基準はおよそ異なるものとなっています。こうした例をひとつひとつ積み重ねて記述していくことで、普段日本に身を置いていると気づきえない論点に出会えるのではないか、と。現代法を比べてみると結果としてあまり日本法と変わらないということであったとしても、そこに至る過程を捨象せず逐一保存していくことで、分析の精度が高まるものと期待しています。成功しているか否かは定かではありませんが。
――なるほど、地道な作業ですね。ところで本書はまず助教論文として執筆され、『法学協会雑誌』での連載、フランス留学を経て刊行されたとのこと。長期にわたって取り組まれてきたわけですが、実際にフランスで生活されて、研究の上で目から鱗のようなことはありましたか?
実は第1部・第2部の通史部分は当初の論文からそれほど大きく隔たるものではありません。あちらで勉強して拡充したのは現代法に関する第3部になります。ここについては、「目から鱗」というよりは、「いろいろ勉強してみたけれどもフランスには理論がない」というのが正直な感想でした。
――ええー、それはどういうことでしょう?
本書で扱ったのは、不当利得といわれる法制度で、物や利益が本来帰属すべき者の許から逸出し、正当な理由がないのに他者の許にある、という場面を規律するものです。日本では、第一に、主として契約を念頭に、かつては物・利益の移転を正当化する理由があったのに、その後それがなくなってしまって、移転された物・利益が不当な利得になってしまったという場面を、第二に、表面的にもそのような理由がないのに、たとえば他人の所有物を使用して利益を得たという場面を問題とします。これに対してフランス法は、前者の場面では覆された契約の後始末の如何が問われているにすぎないと考えて、不当利得法が扱うべき対象とはみなしません。その一方で、後者についても不法行為による損害賠償など別の法制度で片付けてしまうことが多いのです(実はこの点は、本書では不十分にしか扱っていません)。事実、フランスで一般的な適用範囲を誇る(ようにみえる)不当利得制度が形成されたのは、1804年に民法典が成立してから1世紀近く経った1892年でした。とはいえ、この判決の登場も、ある特殊な事案で法制度の欠缺が意識されて、裁判官が対応策を案出せざるを得なくなったがために、半ば苦し紛れに新しい請求権を作り出したというのが真相です。
こうした事情を背景としてか、現代でも様々なルールから「不当利得法」を抽出してくるという学問的営為は展開されておらず、理由なく移転してしまった物・利益の返還が問われる事例毎に裁判例が蓄積され、学説もある意味では場当たり的な仕方でルールを記述することに終始しています。このような法分野に私のような外国人研究者が割って入ることは元来困難で、「うちではこのように説明するけどお宅ではどうなの?」と問いを発してみても空振りに終わることになります。しかし、理論がありそこからすべてが演繹されるという頭の使い方をしている日本の法学研究者の方が特殊なのかもしれず、理論的ではなくとも妥当な判断が集積されていると考えるに至りました。要するに推論の仕方が異なるわけで、そうであれば、無理に日本法に引きつけることなく、フランスで語られていることに真摯に耳を傾けてみた方が生産的に思われたわけです。こういった思考の転換に随分と時間を要してしまったわけですが、本書が日本法からみたフランス法の異質性を強調するものになっていれば、その目的は達せられたと考えます。換言すれば、比較先を掘り下げれば掘り下げるほど、返す刀で比較元に突きつけられる問いが鋭くなる、というのが本書を貫くモチーフです。
――凄いですね、学術書なのになんだかドキドキしてきます。著者おススメの読みどころなど、教えていただけますか。
そうですね、「はしがき」には「不当利得法の別ヴァージョンの探求」というスローガンを掲げました。とはいえ、これは読者として想定される民法研究者に向けてのものでして、自身でやっていて面白かったのは、契約の話なのに国王が出てくる「取消し」のパートです(本書110頁以下)。お読みいただくとわかると思われますが、このパートでは若干大胆な推論をしています。テクストに張り付くことを標榜する本書では異例の部分ですので、ご批判をいただけると幸いです。
――本書は「序」から「結び」まで段落に通し番号があり、その数なんと291。史的諸相、現代的諸相と書き尽くしたかに思えるボリュームですが、今後の展開についてお伺いしてもいいでしょうか?
長いばかりで中身が薄いなあと自戒の念にかられます…。二つだけ言い訳をすると、第一に、法学分野の論文では書き手と読み手との間にデータの共有がないことがしばしばであることを反省して、かなりの紙幅を割いて原テクストを採録しています。批判的に追試をしていただきたいというのがその趣旨になります。第二に、くり返しになりますが、歴史編にせよ、実定法編にせよ、この研究では、あらかじめ大上段の理論枠組みを構えることを自らに禁じています。ですので、個々に展開した分析を、フランス法の特質を描いたより大規模でかつ魅力的なストーリーに回収することが将来の課題になります。具体的には、派生的な諸種の法制度の検討を重ねて、最終的には「所有権」という民法の基礎的な概念にフォーカスしようと考えています。「所有権に基づく返還請求」や「物権変動と不当利得との構造的連関」など、本書でもいくつか種まきをしておきました。
――最後に読者へのメッセージをお願いします。
このコーナーで紹介された他の法学分野のご研究に比して主題の専門性が高く、一般的な読者を獲得しうるものとは考えていないのですが、万が一興趣に叶うようでしたら、どこか特定の数ページでも(それなりに心血を注いだ注も含めて)精読していただけたら嬉しく思います。次が許されるならば、お手にとっていただきやすいものになるよう努めたいと思います(苦笑)。
(2017年10月11日掲載)

齋藤 哲志(さいとうてつし)
東京大学社会科学研究所 准教授
専門分野:フランス法