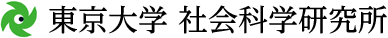案内
新刊著者訪問 第29回
『現代憲法学の位相 国家論・デモクラシー・立憲主義』
著者:林 知更
岩波書店 2016年:6500円(税抜)
このページでは、社研の研究活動の紹介を目的として、社研所員の最近の著作についてインタビューを行っています。
第29回は、林 知更『現代憲法学の位相 国家論・デモクラシー・立憲主義』(岩波書店2016年5月)をご紹介します。
- 主要業績
-
「政治過程の統合と自由—政党への公的資金助成に関する憲法学的考察(1)—(5·完)」国家学会雑誌115巻5·6号, 2002年, 1-86頁;同116巻3·4号, 2003年, 33-116頁;同116巻5·6号, 2003年, 66-153頁;同116巻11·12号, 2003年, 1-86頁;117巻5·6号, 2004年, 1-77頁.

-
「ドイツから見たフランス憲法―ひとつの試論」辻村みよ子(編集代表)山元一、只野雅人、新井誠(編)『講座 政治・社会の変動と憲法―フランス憲法からの展望 第Ⅰ巻 政治変動と立憲主義の展開』(信山社、2017年)157-182頁.

-
“Das Konzept "Verfassungsentwicklung" ― Aus japanischer Sicht“, in: Matthias Jestaedt, Hidemi Suzuki (Hrsg.), Verfassungsentwicklung I – Auslegung, Wandlung und Änderung der Verfassung, 2017, S. 77-86.

インタビューの前に、本書をテーマにすでに社研セミナーが開催されており、林先生がご報告をされました。詳細はこちらをご覧ください。
また、林先生ご自身のウェブサイトでも「ひっそりと特設ページ」を設けられており、先生らしい「若干の解説とセールストーク」をお書きになっています。こちらも是非ご一読ください。では、お話を伺います。
――本書は先生にとって初めての単著ということですが、研究者にとって単著はやはり大きな節目になるものと思います。率直なお気持ちを聞かせてください。
そうですね、本を出すことに対する思い入れは人それぞれだと思います。最近の若い人は、競争も厳しく、なるべく早く最初の業績を本にして、目に見えやすい形で自分の仕事をアピールする圧力に晒されているようで、大変だなあ、と思います。こういうことを言うと人から憎まれるのですが、自分は大学がまだ長閑だった時代に学問的修行をした最後の世代に当たると思います。少しでも早く単著を、というプレッシャーはまだあまり強くなかった反面、自分の学問について覚悟が定まったときに、納得のいく形で自分の仕事を本にまとめて世に問うべきだ、という規範意識がまだ残っていた気がします。「下手なものは出せない」というか、多少大仰な言い方をすると、自分の学者としての存在証明を世に残す、それに値しないようなものは出してはいけない、という意識が、特に私より上の世代にはあったような気がします。今の若い人には、無駄な気負いにしか見えないかもしれませんが…。
そんなわけで、私も最初の単著を出すまでには、随分時間がかかってしまいました。研究室に入って最初に書いた、いわゆる助手論文と呼ばれるモノグラフィー、これを本にする話もあったのですが、その後、最初のドイツ留学を機に、自分の憲法学に対する考え方を根本的な部分で考え直す必要に迫られてしまい、それから約10年、様々な形で短編論文を連作のように書き継ぎながら自分の考えを深めていきました。本書はこの約10年分の仕事をまとめたものです。自分が研究室に入ってから憲法学について考えてきたことのほぼ全て、自分の良い面も悪い面も全部この中に現れていると思います。自分は自分でしかありえない、その自分を欠点まで含めて他人の目の前にさらけ出そう、という覚悟がようやく固まったというところでしょう。あとは、それを受け止めてくれる読者に恵まれるかどうかですが…。まあ、長い目で待ちたいと思っています。
――最初にドイツを研究対象に選んだ理由のひとつは端的に言って面白かったからとのこと、本書では徹底的にドイツ憲法学と向き合っておられますね。
この本が生まれた経緯は、本書の「あとがき」の中で多少詳しく述べました。自分の学問的出発点はドイツ憲法学との出会いです。一般の人は「何でドイツなの?」と思われるかもしれないですね。もっとも、最近はEUの中心国として国際的な地位も目に見えて上昇しているので、割と簡単に納得してくれる人もいるかもしれませんが。
憲法学に限らず、学問としての法学をやろうとする者にとって、ドイツは魅力的な国です。「なぜ?」と訊かれるとなかなか答えにくいのですが…。まず大きな前提として、法学(特に国内法)は、自然科学などと違って、全世界で国境を越えて一つの学問共同体を形成するということがない分野です。国ごとに法律が違う(そもそも言語が違う!)し、直面する問題も様々で、そして国ごとに異なる議論の文化がある。法学は、分野にもよりますが、アングロサクソン中心主義がまだそれほど支配的ではなく、ある種の多文化主義がなお保たれている世界です。その中でドイツ法学の伝統は、学ぶことの多い、魅力的な知的源泉です(まあ、フランス法を主に勉強している人は「フランスの方が魅力的だよ!」と言うかもしれませんが)。あまり説明能力のない比喩で恐縮ですが、クラシック音楽が好きな人にとってドイツ・オーストリアが特別な国であったり、哲学に興味のある人にとってカントやヘーゲルやニーチェやハイデガーや…といった知的伝統が無視できない重みを持つのと、少し似たところがあるかも、という風にでも想像してみてください。
かなり単純化した話になってしまうのですが、19世紀前半、ドイツが諸邦に分裂して統一国家を作ることのできない時代、ドイツ全土で統一した立法をすることが不可能な状況の中で、学問としての法学がその体系や概念を精錬することを通じて法形成を先導する役割を担った、と言われます。以降の知的伝統を振り返って、このような構想力、ある種のビジョンを提示する力をドイツ法学のアイデンティティとして挙げる見解もあるくらいです。これは、フランス革命以降、一般意志としての法律こそに法形成の役割が与えられ、法学が立法に対して従属的な地位に置かれたフランスとは大きく異なる、と対比されることもあります(もちろんフランスにはまた違った学問的面白さがあるのですが)。ここに一体どんな豊かな知的世界が広がっているのか、少し興味を惹かれませんか?
――はい、そうですね、実はそれ以上に先生のドイツ憲法学への情熱に圧倒されてます。
憲法学に関していえば、既に明治の頃から日本の憲法と憲法学がドイツから大きな影響を受けていたこともあり、我々の先人の少なからぬ部分もこのドイツの知的伝統と対決することで自分の学問を作ってきました。今日でも、我々が憲法について考えようとする際に、徹底して考え抜かれた思考、いわば我々の思考にとっての道しるべを、このドイツ憲法学の蓄積の中に発見することもあります。本書は、私が自分なりの形でこの伝統と対決して、自分自身が憲法と憲法学について考える上での一つの座標軸を獲得しようとした、その営みの中間決算というべきものです。
もちろん、ドイツ憲法学の全体を全て客観的に俯瞰するなんてことは不可能です。歴史的な蓄積もぶ厚いし、現代でも毎年膨大な量の業績が産出されています。本書が提示するのは、私の問題意識と切り口というフィルターを通して分析した、いわば「私の見たドイツ憲法学」にすぎません。でも、それはそういうものなのではないでしょうか。これも変な比喩ですが、例えば外国から文学者10人を日本に招いて、「東京」について書いてもらうとする。きっと、10人10様の特色ある東京論が出来上がることでしょう。それぞれ少しずつ違う面に注目しながら、それぞれ東京の一面を鋭く照らし出している。それが主観的な「私の見た東京」にすぎないからけしからん、と批判してみても仕方ないですよね。「客観的」な、誰もが異論を差し挟む余地のない東京論を書こうとしたら、それこそ旅行ガイドみたいなつまらないものになってしまうのではないでしょうか。「対決する」というのはそういうこと、つまり「自分を明かす」ということですから。…もっとも、これは私自身としては正直なところ多少言い訳でもあります。自分の「対決」の深さがまだ足りないために、捉え損なったり、理解が歪んでいる部分があるのではないか、と実のところ怖れてもいます。が、これは今後更に勉強を積み重ねることで自分の理解を高めていく他はありません。
――それで先ほど「中間決算」とおっしゃったんですね。
はい。その意味で本書は、「我々の生きている社会のあり方・構造を学問として捉えようとする上で、憲法学という学問に固有の可能性があるのではないか」、と志を抱いた一人の若者が、知的に最も重要な蓄積を有すると考えたドイツ憲法学と取り組んで20年、自分なりの問題意識を通して一歩一歩獲得していった「私の見たドイツ憲法学」との「対決」の軌跡、として読んでもらえれば幸いです。少しだけワガママを言わせていただくと(笑)、表面的な読み方をする読者には「ドイツはこうなっています」と説明しているだけの叙述に読めてしまうかもしれない文章を前にして、「この著者はドイツ憲法に対していかなる問いを投げかけ、どういう問題意識と切り口から何を切り取ろうとしているのだろう?これが憲法学という学問の根本問題とどこで結びついていると著者は考えているのだろう?」といった点を注意深く読み取ろうとしてくれる読者がいるとしたら、それは著者の立場から言うととても理想的な読者です。本書と真剣に「対決」しようとしてくれる読者には何らかの手応えを残すような本に仕上がったのでは、と自分では自負しています。
――「私の見たドイツ憲法学」ということですが、どのようにご覧になったのでしょう?
そうですね、本書で描き出そうとした「私の見たドイツ憲法学」にどういう特色があるのか…。これは残念ながら複雑すぎて一言で説明することは不可能です。実際に本書を読んでもらうのが一番なのですが、手がかりとしてひとつだけ。これまた乱暴な整理になってしまうのですが、ドイツ憲法学を見ていると、二つの相反する傾向が存在すると感じることがあるのです。ドイツ憲法学には一面で、緻密な概念形成や論理性というか、いわば論証の際の議論の「型」を重んじる傾向がある気がします。で、ここから、条文の解釈や個別の論点の解決に際して滑らかに結論が導出されることをよしとする。このドイツ的な解釈論の枠組みはなかなか便利なので、しばしば他国で輸入され、日本でも近年例えばこのドイツ的文体で基本的人権論を描き切ろうとする試みも有力に登場しています。が、この意味でのドイツ的解釈論は他面で、部分の緻密さに拘泥して全体を見失う、いわば「木を見て森を見ず」に陥る危険が皆無ではない。これは憲法学のように、国の基本構造(constitution)を法学的に捉えようとする学問にとっては重大です。そこで、こうした傾向への反動として繰り返し、学問的な枠組みや言語を組み替えながら、新たな形で「森」を描こうとする試みが登場することになる。これもまたドイツ憲法学の特色です。ドイツは緻密な解釈論の国であるだけでなく、スケールの大きな国家論の国でもあるわけです。
本書が憲法学の学問的可能性として着目するのは、この後者の「森」を描こうとする議論の系譜です。具体的には、ひとつの黄金時代であったワイマール共和国の憲法学―カール・シュミットやスメントの名前に代表される―が出発点として選ばれます。ここにいかなる学問的可能性が隠されており、この系譜を継ごうとする議論が、戦後の立憲国家の定着と安定の中でいかなる困難に直面していったか、学問の課題と方法が変化していく中で、ここでなお「森」を捉えようとする試みにいかなる可能性があるのか…といった問いが、本書の各章を貫く縦糸のような役割を果たしていると思います。これもなかなか説明が難しいのですが…。戦後のドイツ連邦共和国は、ワイマール共和国の失敗やナチスの暴政に対する反省もあって、国家の権力を法によってコントロールするための仕組みを精緻に発達させていく。それは紛れもなく重要な歴史的成果なのですが、他方でそれは我々が社会のあり方を憲法を通して捉えようとする際の前提条件を変えてしまい、また憲法学のイマジネーションを制約し枯渇させていく危険と表裏であったりもするわけです。あくまで比喩的に言えば、ウェーバーじゃないですが、社会のシステムが高度に完成されることで人を縛る「鋼鉄の檻」へと転化する、そこで何か大事な精神が失われる、というのは歴史上も見られることですよね。本書の中心部分は、ここでの変容に対してどのような知的な格闘が行われ、ここから私たち自身が憲法を考える上でいかなる示唆を汲み取れるか、に関わっています。この意味でこれは実はドイツだけの問題ではなくて、現代の私たちが立憲主義や法治国家というものを完成させていく際に、「憲法学という学問によって社会の構造を捉える」という試みが直面しなければいけない諸問題が、ここには集約的に現れている、と私は感じています。憲法理論の可能性を探ろうとする学問的系譜がどこから来てどこへ向かうのか、彼らの命運がどうなってしまうのか。手に汗握る展開を、是非本書を手にとってあなた自身の目で確かめてみてください(笑)。
――ところで、憲法というとやはり改正問題が避けて通れない気がします。ドイツでは戦後60回も改正されていると知り驚きました。日本は0回ですね。フランスもアメリカも少なからず改正されています。このあたりはどういうことなのか教えてくださいますか。
良い質問です。が、これも一言で答えるのは不可能です。敢えて簡単に言ってしまえば、憲法がそれぞれの社会で果たす機能が異なれば、それに応じて改正する必要性も異なる、という点が大きいと私は考えています。「具体的な事柄を詳細に定めた拘束力ある法」は社会の変化に応じて小まめに改正する必要性も大きいけれども、「国のあり方についての理念を書いた抽象的文書」は別にそう慌てて変える必要もない。憲法改正問題を論じる前にまず我々が考えるべき問題は、「我々は『憲法』という文書にどのような機能を与えることを望んでいるのか」という問題だと思います。すごく大雑把に言ってしまえば、戦後のドイツは憲法を大幅に前者の方向へと発展させたのに対して、日本国憲法の下における憲法の運用のあり方は後者の性格を大幅に残していると感じます。本当にそれでいいのか、あるいはどこかに改めるべき点があるのか、というのが実は一番大事な点だと思うんですよね。憲法の文字を変える、いや変えなくても大丈夫だ、云々というのは多分その先の問題です。憲法が日常的にどう機能しているかについて大して関心も知識も持たない人が、改正の是非については急に熱く語り出す、ということがもしあるとしたら、それは困ったことです。本書の終章でも少し論じていますので、よろしければ読んでみてください。
――「終章 戦後憲法を超えて」ですね。
はい、しかしこの「改正の是非」にはもっと重要な問題が潜んでいます。日本の憲法論議を聞きながら、次のような疑問を持ったことはないでしょうか。「日本社会ではなぜ憲法問題というと改正の是非ばかりが論じられるのだろう?どうして護憲か改憲かといった手垢のついた古い対立枠組みが繰り返し登場するのだろう?そもそも憲法について他の国でも同じように論じられているのか?私たちの憲法への向き合い方は、実は世界的に見るとすごく特殊なものなのではないか?」、等々。
こうした疑問を多少とも掘り下げて考えるためには、いったん自国の問題状況を棚上げして、よその国がどうなっているか腰を落ち着けて勉強してみるのが良い方法です。他者を知ることによってこそ、我々は自分自身をよりよく理解することができるからです。本書の主題は、実はこうした点にも拘わっています。我々は他の国、例えばドイツをよく知ろうとすることで(別にドイツ以外でも良いのですが)、日本がいかにそれと違っているかを、いわば異化された形でまざまざと意識することができる。時事的な憲法問題に対してすぐに安直な答えを求めようとするせっかちな人は別として、憲法について本当に一段深く考えたい人は、一見遠回りに見えるとしても、他国を勉強することを避けるべきではありません。本書は、序章で日本の戦後憲法について考察し、本論でドイツ憲法学を長く分析した後、最後に終章でもう一度日本の問題状況に帰ってくる、という構成を取りました。いったんドイツを経由した目で戦後日本をもう一度眺めた時に、どのような姿が見えてくるのか。真面目に読んでくれた読者に、是非感想を聞いてみたい気がします。
――最後に読者へのメッセージも含めて今後の抱負をお聞かせください。
20年くらいドイツ憲法学を中心に勉強してきたのですが、実はドイツはドイツで結構特殊な国なんですよね。ドイツでも、比較的若い世代の研究者を中心に、外国を参照することによって自国の伝統をもう一度批判的に見直す、という動きが過去十数年の間に強まっていて、こうした中から学問的なイノベーションも生まれつつあるように見えます。本書もドイツでのこうした新しい学問的な動きから多くの刺激を受けました。そうしたこともあって、自分の学問的な幅を広げるために、私もドイツだけでなく少しフランス憲法学の勉強を始め、パリに在外研究にも行かせてもらいました。ここから何が生まれてくるか、自分ではまだ手探りの状態で不安も大きいのですが、焦らず時間をかけて自分の憲法学をより豊かなものにしていきたいと願っています。
とりあえず次は、最初の作品である助手論文を、学術誌で公表してから十数年ぶりにもう一度「解凍」して単行本として刊行したいと思っています。テーマは政党政治で、今なお日本にとってアクチュアルなテーマですね。書き直しにどれくらい時間がかかるかわかりませんが、また次作で読者と出会えることを楽しみにしています。
(2017年12月19日掲載)

林 知更(はやしとものぶ)
東京大学社会科学研究所 教授
専門分野:憲法学・国法学